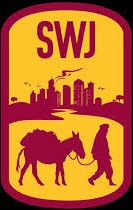戦術的塹壕キラーから戦略的戦争勝利者へ (Modern War Institute)
ロシア・ウクライナ戦争に関わる論稿や報道を見ても、ドローンの軍事的な利用価値があるとの認識を、誰も否定するところではないだろうと思える。「air littoral(MILTERMでは沿空域と表現)」という用語は、戦場空間の中の1,000フィートまでの一部の空間を表す言葉として定着しつつあるようにも感じる。「2025年4月30日付国防長官の覚書「米陸軍の変革と取得改革」」にも、沿空域支配(air-littoral dominance)の達成を2027年までに行うことを挙げている。
ドローンは、この「air littoral」内を意のままに動かして、情報を収集しターゲティングに活用し、各種火力の能力発揮に結び付け、更には弾薬を抱え込み地上の兵士や装備(高価な地上待機の飛行機や精密なシステム機器)を殺傷し破壊するいわゆる消耗戦(attrition warfare)に利用されていると理解するのが一般的なものだと思える。
ここで紹介するのは、ドローンを単に消耗の道具(tools of attrition)だけではなく、新時代をリードできる機動戦(maneuver warfare)の要素として考えること、つまりは戦術的視点にとどまらない、作戦術(operational art)の視点からの思考を促す論稿である。
論考の後半に「この術(art)[作戦術]を進歩させるには、ウォーゲームや演習で大胆な実験を行う必要がある。それは、ドローンを歩兵、装甲、機械化部隊と意図的に組み合わせ、ドローンを後付けではなく、作戦デザインの中心的な部分として使用することを意味する。そうすることで、ドローンは極めて効果的な戦術的厄介者にとどまらず、21世紀の戦いの決定的なツールへと変貌を遂げるだろう」とあるが、新しい諸兵科連合(combined arms)の考察を促すものでもあると考える。(軍治)
![]()
戦術的塹壕キラーから戦略的戦争勝利者へ:ドクトリン、作戦術、そして明日のドローンが可能にする機動戦
From Tactical Trench Killers to Strategic War Winners: Doctrine, Operational Art, and Tomorrow’s Drone-Enabled Maneuver warfare
Antonio Salinas, Mark Askew and Jason P. LeVay | 08.04.25

画像:2025年1月23日、カリフォルニア州フォート・アーウィンの国立訓練センターで、HERO-120徘徊型弾薬システムを発射する第1歩兵師団所属の兵士。 (クリストファー・ベイリー(Christopher Bailey)米陸軍上等兵) |
アントニオ・サリナス(Antonio Salinas)は現役の米陸軍将校で、ジョージタウン大学歴史学部の博士課程に在籍。博士課程修了後は、国立情報大学で教鞭をとる。サリナス(Salinas)は米海兵隊と米陸軍で27年間の軍務経験があり、歩兵将校、米陸軍士官学校歴史学科助教授、戦略情報将校を歴任し、アフガニスタンとイラクでの作戦経験を持つ。著書に『Siren’s Song: The Allure of War』、『Boot Camp: The Making of a United States Marine』、『Leaving War: From Afghanistan’s Pech Valley to Hadrian’s Wall』などがある。
マーク・アスキュー(Mark Askew)は現役の陸軍将校であり、戦史家である。装甲将校、米陸軍士官学校歴史学科助教授、陸軍戦略家として20年以上の軍務経験があり、イラクでの作戦経験もある。テキサスA&M大学で戦史の博士号を取得し、現在は米陸軍未来司令部に勤務。
ジェイソン・P・ルベイ(Jason P. LeVay)は、フォート・レーベンワースの米陸軍指揮参謀学校で統合ドクトリンを教え、カンザス州立大学安全保障研究プログラムの博士課程に在籍。ワシントン大学で学士号を取得し、イェール大学と国家情報大学で大学院を修了。
ここで述べられている見解は著者の見解であり、米陸軍将校学校、米陸軍省、国防総省の公式見解を反映するものではない。
![]()
歴史を通じて、技術がドクトリンを凌駕したとき、決定的勝利の夢はしばしば打ち砕かれてきた。第一次世界大戦では、ドイツのシュリーフェン計画で描かれた迅速な勝利の約束は、機関銃と砲兵によって打ち砕かれ、ヨーロッパの戦場を迷路のような塹壕線に変える膠着状態に陥った。1916年までに戦車が解毒剤として登場し、カンブレーのような会戦で無人地帯を横断して歩兵を支援するようになっても、適切なドクトリンと連携がなければ、戦術的勝利を作戦的突破口(operational breakthroughs)に変えることはできなかった。
23年後の1939年、戦車はもはや歩兵支援のための目新しいものではなくなった。近接航空支援(close air support)と組み合わされることで、決定的な機動(decisive maneuvers)を形成し、突破口を開くことが可能になった。戦いを変えたのは機械だけでなく、ドクトリンや組織も同様で、単に領土を奪うだけでなく、敵の大編成を破壊することを可能にした。
この歴史的背景は、今日の、そして明日の戦場におけるドローンの役割を理解するための強力な枠組みである。ドローンは、ウクライナの塹壕戦線やその周辺で壊滅的な消耗をもたらすツールであることが証明されつつあるが、やがて機動戦の次の進化を可能にするかもしれない。第一次世界大戦における戦車と同様に、ドローンは戦術的新機軸として登場し、恐ろしいほどの致命的な効果をもたらしたが、その効果は限定的だった。そして、第二次世界大戦における戦車のように、適切なドクトリン、組織、作戦コンセプトで強化されれば、ドローンは攻勢的な突破口と搾取の条件を確立するのに役立つだろう。
ドローンはすでに、塹壕内の部隊を殺害したり、車両を無力化したりすることができることを示しており、これは消耗に寄与する戦術的行動である。しかし、消耗(attrition)だけでは、たとえ規模が大きくなったとしても、米国を含むほとんどの西側諸国軍が決定的な成果を得るには、迅速でも安価でもない。このアプローチに代わる方法の一つは、敵の編成と、それらの編成が戦闘効果を維持するために依存している重要なサブシステムを混乱させ、崩壊させることである。これは、敵部隊の指揮・統制を断ち、兵站を断ち、敵部隊を孤立させ、再編成や作戦地域の重要な部分を強化できないようにすることを意味する。同時に、友軍はこうした機会を利用して敵の防御を破り、敵部隊が反応するよりも早く敵部隊の戦闘システムの重要な部分を破壊する。このようにして、作戦上の成功は、反復可能であれば、有利な戦略的結果に結びつく。
消耗(attrition)と機動(maneuver)を現代戦の対立モデルとみなすのではなく、機動(maneuver)は敵の能力の迅速な破壊を可能にすることで、消耗のアプローチ(attritional approaches)を補完することができる。脆弱性を作り出し、それを利用することで、機動(maneuver)は有利なコストで敵の能力を効率的に破壊することを可能にし、旅団、師団、軍団全体を詳細に破壊することにつながる可能性がある。このアプローチでは、地上戦での勝利は、作戦的突破口(operational breakthroughs)を開くための条件を整えることにかかっており、現代では、これは攻勢的機動戦(offensive maneuver warfare)のためにドローンの潜在能力を最大限に開発することを意味する。
ロシアがウクライナで決定的な勝利を収めようと奮闘していることは、3つの永続的な、しかし現在では激化している主要な作戦上の課題を浮き彫りにしている。第一に、近代国家は広範な前線を守ることができるため、攻撃可能な側面が不足し、攻撃側はコストのかかる侵入機動(penetration maneuvers)のリスクを強いられる。第二に、侵入作戦(penetration operations)には莫大なコストがかかるため、その攻略が困難である。第三に、防衛側は迅速な精密火力と反撃で対応できるため、攻撃側が作戦効果を発揮する前に攻勢を食い止めることができる。このような困難な状況を踏まえると、機動(maneuver)に求められるのはスピードだけでなく、大規模に敵システムを孤立させ、混乱させ、破壊することである。
ドローンが可能にする機動(drone-enabled maneuver)は、側面を迂回し、静的防御を圧倒し、そして重要なこととして、敵の予備兵力の再配置を防ぐために重要なセクターを孤立させることを可能にすることによって、この3つの解決策を提供することができる。そして重要なことは、敵の予備兵力の再配置を防ぎ、攻略に成功する舞台を整えることである。沿空域(air littoral)は、地上戦における新たな攻撃可能な側面となる。
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)の可能性を活用するために、安全保障の専門家は、ウクライナの塹壕戦における一人称視点でのドローンの観測に基づいて狭い結論を出さないように注意すべきである。これは、ソンムで泥の中をのろのろと進む戦車を見て、ドローンでは敵部隊の破壊は不可能だと決めつけるようなものだ。
ドローンは、作戦的レベルで効果的に運用すれば、20世紀に戦車が達成したことを21世紀の戦い(twenty-first-century warfare)で実現しようとしている。ドローンが消耗の道具(tools of attrition)から、ドローンが可能にする作戦術の道具(instruments of drone-enabled operational art)へと進化すれば、我々のドクトリンにあるように、敵のシステムを迅速かつ正確に解体することで、機動戦(maneuver warfare)の新時代をリードすることになる。ドローンを戦術的な厄介者から、作戦的崩壊および戦略的崩壊を引き起こしかねない決定的な戦力増強機に変えることこそ、課題であり、機会なのである。
空中の羽音(hum)は大きくなり、火力だけでなく、ドローンが可能にする作戦的突破口(drone-enabled operational breakthroughs)の夜明けをもたらしている。
ウクライナ:塹壕戦でのドローン
ウクライナの戦場では、ドローンが様々な任務を遂行できることが実証されたが、迅速な機動と搾取を可能にする能力は依然として限定的である。これまでのところ、ウクライナでの戦争は、軍事史上最も広範なドローンの使用を示しており、戦争の戦術的、作戦的、戦略的レベルにわたって致死性のプレビューを提供している。ドローンは、インテリジェンス、監視、偵察において、そしてターゲッティングにおいて、さらにはロシアの空軍基地に対する縦深打撃の役割を担っている。
しかし、広く使用され、死傷者を出す能力があるにもかかわらず、作戦的機動(operational maneuver)のまとまった枠組みからはほとんど切り離されたままだ。主要な編成の崩壊、包囲、破壊につながる戦場の裂け目を作り、利用し、維持するためにドローンが使われたのを、我々はまだ見たことがない。紛れもなく、ドローンは消耗(attrition)を加速させ、優れた火力統制を提供し、何万人もの戦闘員を殺害してきた。ただ、戦術的混乱を作戦的獲得に結びつけるような衝撃(shock)を与えることはできなかった。
しかし、だからといって、それができないわけではない。第一次世界大戦中の戦車の運用に見られるように、兵器システムの初期配備には必ずしも最善のドクトリンが伴うとは限らない。最近ロシアがクルスク近郊で行ったドローン可能にした作戦には、ドローンが可能にする機動の約束(the promise of drone-enabled maneuver)を限定的に垣間見ることができる。したがって、課題は、ドローンが戦術的に何ができるか、あるいは作戦的に何ができるかではなく、戦術的効果を作戦的・戦略的成功に変えるドクトリンを作成し、訓練し、装備し、実行することにある。
機動戦の進化(maneuver warfare evolution)の次の段階が進展するのに、23年もかかることはないだろう。世界の陸軍がドローンが可能にする戦場(drone-enabled battlefield)に備えて装備し、組織し、訓練することを競い合う中で、1、2年以内に実現するかもしれない。
ドローン戦術を作戦的機動のコンセプト(concept of operational maneuver)に最初にパッケージ化した軍隊は、相手の軍隊をズタズタにするだろう。ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)の到来の約束(promise)、そして脅威は現実的であり、それは我々が考えるよりも近い。
機械化された機動戦からドローンが可能にする機動戦へ
第二次世界大戦における機械化機動戦(mechanized maneuver warfare)は、決して戦車だけのものではなかった。それは、スピード、衝撃、包囲に重点を置いたドイツ流の戦法(German style of warfare)であった。軍事史家のロブ・シティーノ(Rob Citino)が指摘するように、電撃戦(Blitzkrieg)は1939年に突然出現したものではなく、ベーヴェーグング・クリーク(Bewegungskrieg)(移動の戦争(war of movement))とケッセルシュラハト(Kesselschlacht)(大釜の会戦(cauldron battle))の現代的表現であり、敵部隊を包囲して排除することを意図していた。18世紀以来、ドイツの軍事思想は敵を包囲して破壊する迅速な機動を重視し、領土を占領するよりも軍隊を崩壊させることで戦争を迅速に終結させることを目指していた。
連合国の計画担当者は、自らの好む戦争の方法を大幅に強化したこの新しい能力をドイツがうまく運用したことを考慮に入れなければならなかった。これは、ドイツが最終的に有利な条件で戦争を終結させるための実行可能な戦略と戦場での作戦を調整することができなかったにもかかわらず、米国の思想家が新しい能力の運用コンセプトを開発する際に考慮すべき教訓である。
では、合衆国はどのようにドローンを使って米国の戦争の方法を強化できるのだろうか?ドローンは現在、沿空域(air littoral)で敵の側面をつぶす機会を作り出し、それを活用する部隊を可能にすることで、機動戦を行う可能性を提供している。伝統的に側面とは理解されていないが、沿空域(air littoral)(1,000フィートまでの低空で争われる空域)は、継ぎ目を露出させ、新たな攻撃軸を可能にする新たな機動空間(maneuver space)として機能することができる。
何十年もの間、地上部隊は重要な場面で息を潜め、近接航空支援(close air support)が到着して敵の防衛を制圧するのを待ってきた。ドローンを賢く使えば、数時間単位ではなく、数分単位で、持続的で、即応性があり、正確な近接航空支援を提供することができる。これによって、部隊は沿空域(air littoral)での航空優勢(air superiority)を維持することができるが、より重要なのは、地上での衝撃、機動、テンポを維持することである。このように、ドローンは機動戦の次の時代を切り開く空中ハンマー(the airborne hammer)となりうる。
ドローンが塹壕や車両への限定的な打撃以上の用途に使われる可能性は、すでに初期段階から示唆されている。ウクライナがロシアの飛行場を攻撃し、イランの防空網のイスラエルの打撃は、車両が陸上を基盤とする空母(land-based aircraft carriers)として機能し、敵地の奥深くまで正確な航空兵力を送り込む未来を示唆している。これらの作戦は、航空戦(air warfare)と陸上戦(land warfare)の次の段階がどのようなものになるかを予見させる。
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)には、車両で持ち運び可能で、滑走路に依存せず、典型的な一人称視点のドローンよりも大きなペイロードを搭載し、より広い範囲で活動できる、第2グループと第3グループの無人機システムである重ドローンが必要になる。このようなドローンは、単発使用の徘徊型弾薬(single-use loitering munitions)から、繰り返し使用し永続的に存在するようにデザインされた戦術的マルチロール・プラットフォームまで様々である。
ドローンはすでに打撃任務を遂行しているが、そのほとんどは、高速で移動する地上作戦を支援する決定的な効果を生み出すことができるペイロードを提供することができないため、より大型のドローンは、タコ蛸(foxholes)や塹壕を越えて殺傷能力を拡大することになる。このような重量のあるドローンは、第二次世界大戦中に戦車や急降下爆撃機が敵部隊の重要な部分を孤立させ破壊したように、重要なポイントで決定的な火力を提供するだろう。
ドローンとそれを輸送する部隊は、高速で移動する機甲部隊、機械化部隊、歩兵部隊と完全に統合され、中央統制の近接航空支援(close air support)から遅れることなく、常時偵察と打撃能力を提供しなければならない。これらのドローンは、前方を偵察し、防御を制圧し、敵の編成を孤立させ、精密な打撃を実行し、前進する部隊が勢いを維持し、リアルタイムで適応できるようにする。航空支援を要請する代わりに、編成は自らの航空兵力を直接前進に運ぶ。
小型で機動性の高い、陸上を基盤とするドローン空母(drone carriers)として機能する車両は、大隊や中隊レベルに組み込まれた移動発射プラットフォームであり、飽和攻撃をオンデマンドで開始し、カオスの回廊と機動部隊が利用できる機会を作り出すことができる。
ドローンは、ジャミング、ドローン対ドローンの消耗、密生した植生や強風、悪天候での性能低下など、紛争環境での重大な脆弱性に直面している。ドローンが可能にする機動(drone-enabled maneuver)は、沿空域(air littoral)における移動の自由(freedom of movement)のために闘わなければならない。それでも、地上機動と統合され、電磁支援によって支援される場合、ドローンは、脆弱ではあるが、機会の窓(windows of opportunity)を作ることができる柔軟な機動打撃オプションを提供する。
最も重要なことは、指揮構造(command structures)がドローン打撃を作戦的機動(operational maneuvers)に完全に組み込まなければならないということである。その到達目標は、前線陣地を破壊するだけでなく、敵の指揮システム(command systems)や後方地域を混乱させることであり、それによって敵の迅速な孤立、包囲、組織的崩壊の条件を作り出すことである。
実際には、先陣を切って侵入する地上部隊が従来の見通し線兵器で攻撃を開始する前に、敵部隊を孤立させ、再配置、増援の受領、追加の対抗移動障害物の設置、または作戦的火力の恩恵を受ける能力を阻止することができる陸上を基盤とするドローンや徘徊型弾薬(loitering munitions)が先行することになる。このような作戦の条件形成の到達目標は、攻撃地点を制圧するだけでなく、戦術的な成功を利用し、作戦上重要な目標を奪取するのに十分な時間と十分に広い移動回廊を友軍に与えることである。
旅団や師団の迅速な機動を促進するため、ドローン対応の工兵大隊は、ドローン配送線爆薬(line charges)を展開し、迅速かつ効果的に地雷原を大規模に除去することができる。これらの部隊は、改良型地雷除去線爆薬の運搬と展開が可能なドローンを装備しており、地雷原と確認された地雷原の上空に爆薬を飛行させて正確に爆発させ、工兵を直接火力や砲兵火力にさらすことなく、装甲部隊と機械化部隊のための通路を作り出すことができる。
このドローンを活用した突破部隊は、師団が広範な戦線で同時に複数の進路を確保し、攻撃の勢いを維持し、地雷原でのボトルネックを減らすことを可能にする。旅団や師団は、かつては遅々として進まず危険だった突破プロセスを、戦闘力を維持し作戦テンポを持続させる迅速で連携した作戦に変えることができる。
ロシアとウクライナの双方は、このような運用モデルに必要なツールをすでにいくつか保有しているが、双方とも決定的な成果を上げるには至っていない。ドローンが作戦の突破口に使われるのをまだ見ていない重要な理由のひとつは、双方が空中の沿空域(air littoral)を統制できないという相対的な無力さである。この空間、そして理想的にはその上空も統制できなければ、敵の火力によって固定されるのを回避したり、敵の予備兵の到着を防いだりするのは非常に難しくなり、作戦のテンポや勢いを妨げることになる。
ドローン対応師団(Drone-Enabled Division)の構築
このビジョンを実現するためには、我々の戦力構造(force structure)を見直す必要がある。現代の米陸軍師団には通常、2~3個旅団戦闘チーム、師団砲兵、戦闘航空旅団、後方支援旅団、師団司令部が含まれる。すべての旅団戦闘チームは、おそらく有機的なドローン・アセットによってドローン対応になるだろうが、重要な進歩には、決定的で重量のあるドローン作戦のために特別にデザインされたドローン打撃旅団(drone strike brigade)が必要である。
ドローン打撃旅団は6つの専門大隊で構成され、それぞれが特定の任務を遂行するためにより重いドローンを装備する。重ドローン打撃大隊は、戦場での深く正確な打撃のために大型ドローンを運用する。重ドローン隔離・阻止大隊は、攻撃回廊の確保、沿空域(air littoral)の優越と側面警備の維持、敵の反撃に対する火力支援に重点を置く。
ドローン空母大隊(drone carrier battalion)は、例えば高機動砲ロケット・システムを搭載するトラックなどの改造車両を、空中の沿空域(air littoral)を飽和させるための移動式陸上を基盤とするドローン発射機として運用する。旅団はまた、継続的な情報、監視、偵察、および電磁スペクトルの支配を提供するために、ドローン偵察大隊および電子戦大隊を含むだろう。
ドローン対応の工兵大隊は、ドローンを使って地雷原を減らし、設置し、機動性を向上させ、領域拒否作戦を実施する。最後に、専用のドローン後方支援大隊は、ドローン固有のニーズに合わせた後方支援、メンテナンス、補給を通じて、高い出撃率を促進する。
この構造により、師団は、高い作戦テンポを維持しながら、奥深く、システムを孤立させたり、分断したりする打撃を実行できるドローンが可能にする機動部隊(drone-enabled maneuver force)に変貌する。コンセプトの実証として、この能力を大隊に導入し、その専門分野を中隊にサービスさせることで、これらの能力の一部を旅団に再現することもできる。
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)が必要とするのは、新しいツールだけではない。最も重要なことは、階層を超えた指揮、統合、機動の新しい方法が必要になることである。成功するためには、ドローン部隊は機動部隊とともに訓練し、移動し、沿空域(air littoral)支配のシェアを拡大し、防護しなければならない。これは、ドローン能力を単に火力支援アセットとしてサイロ化するのではなく、分隊から師団に至るまで、諸兵科連合(combined arms)の計画策定サイクルとリハーサルに織り込まなければならないように、指揮構造(command structures)を再考することを意味する。
コブラ作戦と死のハイウェイ――すべてが同時に
作戦的レベルでのドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)は、コブラ作戦(Operation Cobra)や死のハイウェイ作戦(Highway of Death)のような、20世紀で最も鋭利な軍事的衝撃の最も決定的で壊滅的な要素を、拡張可能で反復可能な、持ち運び可能な作戦術(operational art)に融合させるだろう。
1944年の連合軍のノルマンディーからの脱出作戦であるコブラ作戦は、防衛線を弱体化させる航空支援の破壊力を実証し、膠着状態を数日以内の素早い崩壊に変えた機甲部隊への道を開いた。1991年の「砂漠の嵐作戦(Operation Desert Storm)」における「死のハイウェイ(Highway of Death)」は、退却する部隊に対して容赦なく使用され、ほとんど抵抗することなく隊列を破壊したとき、現代の航空兵力の正確さを実証した。
ドローンが可能にする機動(drone-enabled maneuver)で最も重要な側面のひとつは、打撃の能力だけでなく、永続的で信頼性が高く、実行可能なインテリジェンスをリアルタイムで提供する能力である。専用のドローン旅団は、戦場の奥深くまで見通し外のインテリジェンスを提供し、指揮官がリアルタイムで敵の動きを見て理解することを可能にする。このような継続的なインテリジェンスの流れがあれば、指導者は敵の編成の動きや亀裂を発見し、敵のバランスが崩れている間にそれを利用することができる。
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)は、戦場の暴力パターンを高度な機動戦闘のダンスへと変えるだろう。長距離、消耗品、より重量のある打撃用ドローンは、今日の戦争で見られるよりも大規模で縦深の深い敵対者の防衛を制圧し、破壊することができる。重量のあるドローンは、コブラの絨毯爆撃(Cobra’s carpet bombing)のように前方の防衛を破壊するが、機動部隊のために通路を空けておく精度を持つ。防衛側が再配置や撤退を試みると、ドローンは道路を致命的な罠に変え、「死のハイウェイ(Highway of Death)」をより大規模に再現する。
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)では、20世紀の空地戦闘(air-land combat)の最も過酷な瞬間は、もはや戦域を一変させるような稀な出来事ではなくなる。恐るべきスピードと効率で敵のシステムを急速に不安定化させ、崩壊させるための、日常的でスケーラブルな作戦となるだろう。
ドローンの作戦術の開発
ドローンが可能にする機動戦(drone-enabled maneuver warfare)への道は、ドローンのドクトリンと作戦術(operational art)の開発を要求している。戦術的勝利を作戦的突破口(operational breakthroughs)と戦略的成功(strategic successes)に変える、ドローンが可能にする戦役(drone-enabled campaigns)の意図的なデザインと運用である。戦術(tactics)と戦略(strategy)をつなぐものとして、作戦術(operational art)は従来、機動を使って相手の戦線を不安定にし、通信回線を切断し、敵のシステムの一貫性を破壊することを意味してきた。ドローンは今、孤立した打撃としてではなく、大規模な混乱、麻痺、搾取を引き起こすための重要なツールとして、この枠組みに組み込まれなければならない。
これには、単に嫌がらせのためだけでなく、搾取のための経路を作るために、重要なポイントにドローンを大量に配置するコンセプトを開発する必要がある。キル・ボックスを作戦上の移動通路に変え、ドローンのスウォームが敵の装甲車や歩兵、兵站輸送隊、砲兵の再配置を狙い、前線を越えても敵の反応と釘付けを維持できるようにする必要がある。
ドローンの作戦術(drone operational art)を開発するには、タイミングとテンポを再考する必要もある。地上部隊が間断なく隙を突いている間、ドローンは絶え間なく圧力をかけ続ける。このアプローチでは、防衛側は継続的な危機状態に追い込まれ、崩壊が加速する。ウクライナの戦場空間(battlespace)はドローンで飽和状態にあるが、技術の存在だけでは不十分なため、崩壊は起きていない。
我々は、この能力の初期段階での使用を目の当たりにしている。戦車と同様、現在我々が目にしているのは、大規模な生産能力を持つ敵対者が将来的に発揮する可能性のある能力のほんの一部にすぎないかもしれない。さらに、これらのシステムは生産が容易で、装甲に比べ非常に安価であり、多くの場合、急速に再利用できるデュアルユース技術として利用可能である。この新しい規模が、軍隊によって書かれ、訓練され、リハーサルされたドクトリンと組み合わされ、より成熟したAI能力で強化されたとき、ドローンは攻勢的機動の実行可能性を回復する重要な材料として、その潜在能力をフルに発揮できるようになるだろう。
この術(art)[作戦術]を進歩させるには、ウォーゲームや演習で大胆な実験を行う必要がある。それは、ドローンを歩兵、装甲、機械化部隊と意図的に組み合わせ、ドローンを後付けではなく、作戦デザインの中心的な部分として使用することを意味する。そうすることで、ドローンは極めて効果的な戦術的厄介者にとどまらず、21世紀の戦いの決定的なツールへと変貌を遂げるだろう。
ウクライナの塹壕はフランドルの泥沼を彷彿とさせるが、その上空に響くドローンの音は、100年以上前のフランスのぬかるんだ野原での戦車の振動がそうであったように、先の変化を告げている。ドローンは塹壕の兵士を殺す能力があることは証明されているが、それだけでは十分ではない。現代の戦争に勝つには、陣地を占領するだけでなく、システム全体を解体し、敵を混乱させ、そして破壊する必要がある。
1940年、戦車がカンブレーの泥濘を這いながらフランスを駆け抜けたように、ドローンは今日、ウクライナ上空でブンブンと音を立てて打撃し、将来の姿を予感させている。問題は、ドローンが人を殺せるかどうかではなく、軍隊を壊すためにドローンを使えるかどうかである。
今日の防衛計画策定を支配している不測の事態は防勢的かもしれないが、攻勢的な行動が我々の到達目標を達成する唯一の方法かもしれない瞬間がやってくる。ウクライナの塹壕を越えて、明日の作戦術(operational art)に目を向けなければならない。敵のシステムを分断し、隙を突いてスピードを上げ、敵対者が反応する前に崩壊させる機動戦を、ドローンがいかに可能にするかを問うのだ。
その窓は狭く、変化のペースは速く、賭け金は非常に高い。ドローンが可能にする作戦的突破口(drone-enabled operational breakthrough)を最初に習得した軍隊は、単に次の会戦(the next battle)に勝つだけでなく、戦いの実践(practice of warfare)そのものを再定義することになるだろう。
空から聞こえる羽音(hum)はますます大きくなり、戦争が我々を変容させる前に、戦争を変容させるチャンスがやってくる。