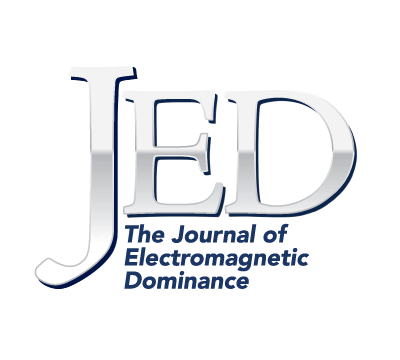スマートに闘う (Marine Corps Gazette)
2024.7.8 に公表の「米海兵隊人工知能戦略」にある「スマートに闘う」ことについて述べられたMarine Corps Gazetteに掲載の記事を紹介する。作戦環境は情報環境でもあると云われる現代において情報を如何に活用して闘えるようにするかが大きなカギとなる。(軍治)
![]()
スマートに闘う
Fighting Smart
21世紀の競争、抑止、戦いにおける情報
Information in 21st-century competition, deterrence, and warfare
by LtGen Matthew G. Glavy & Mr. Eric X. Schaner
Marine Corps Gazette • April 2024
マシュー・G・グラヴィ(Matthew G. Glavy)米海兵隊中将は情報担当副司令官である。
エリック・X・シャナー(Eric X. Schaner)は退役インテリジェンス将校で、現在は情報担当副司令官内の計画・戦略部門の副部長を務めている。
戦いの性質(character of warfare)は、10年前にはほとんどの人が想像できなかったほど速いペースで変化している。過去4年間だけでも、ロシアはウクライナに侵攻し、アゼルバイジャンはアルメニアとの紛争を再開し、ハマスはイスラエルを攻撃し、フーシ派は紅海を妨害し、中国は南シナ海でフィリピンの船舶に体当たり攻撃を行った。これらの出来事、そして中国が台湾海峡の中間線を頻繁に越えるようになったことは、近年の世界の変化を浮き彫りにしている。これらの出来事から、戦いの性質(character of warfare)がかつてないほど速く、より密接に結びついていることが分かる[1]。
戦争は依然として人間の意志による究極の争いであり、長期にわたる場合もあるが、センサーからシューターまでの戦場での交戦はかつてないほど速く起こり、マルチドメインの効果が収束することで迅速に決着する[2]。キル・チェーンは複雑であるが復元性のあるキル・ウェブへと進化している。国家および非国家主体は、成熟しつつある精密打撃体制を改善するために、すぐに利用可能な能力を組み合わせることで、キル・ウェブを構築している。国家主体にとって、これには、広く入手可能な低コストのセンサー、公開されている情報、市販のセンサー・データ、ソーシャル・メディア、および国有のセンサー・データを使用して、低コストの無人航空システムや徘徊型弾薬(loitering munitions)から長距離の極超音速ミサイルや弾道ミサイルに至るまで、幅広い精密スタンドオフ兵器を使用することが含まれる。
ソーシャル・メディアなどの高度に接続された技術は、ナラティブをめぐる会戦(the battle over narratives)を根本的に変えつつある。前述の紛争から東アジアにおける数多くの潜在的な火種に至るまで、競争や紛争の対抗者(opponent)とその支持者たちは、動画、画像、その他のコミュニケーション手段を通じて、絶え間なくメッセージを浴びせられている。これらのメッセージは、敵に撤退を促したり、ライバル勢力に屈服させたり、あるいはその両方を狙っている。こうした変化の中心にあるものは何だろうか?
情報、そして情報を用いた支配をめぐる会戦(the battle to dominate with information)は、戦いの性質(character of warfare)を根本的に変えつつある。情報獲得をめぐる技術的かつ認知的な闘いの両方に勝利した側が、会戦に勝利し、戦争に勝利する可能性が最も高い。対等な敵対者(peer adversaries)はこれをよく理解している。彼らは、世界規模で拡散するセンサー、豊富なデータ、事実上無制限の計算能力、人工知能、ソーシャル・メディア、そしてハイパーコネクティビティを活用し、自らの能力を適応、進化させ、場合によっては変革することで、歴史的な米国の軍事的優位性を相殺しようとしている[3]。
米海兵隊は、高度に接続した世界において、今日の技術主導の課題に対応するために、適応を続けなければならない。情報を活用して決心の優位性(decision advantage)を達成し、マルチドメインの効果を組み合わせ、敵対者よりも早くキル・ウェブを閉鎖し、そしてナラティブに影響を与える米海兵隊員は、現在の戦い(current warfare)そして将来の戦い(future warfare)において優位性を達成するだろう。米海兵隊の適応は、現在の出来事から学び、データと情報へのアクセスがもたらす機会を活用することで継続される。米艦隊海兵部隊(FMF)は、海兵遠征軍(MEF)情報グループや海兵沿岸連隊などの部隊を通じて、現在これを実践している。我々は、さらに努力を重ねなければならない。
情報担当副司令官(DC I)に対する総司令官のタスク
こうした課題を見越して、米海兵隊は2017年に情報担当副司令官(DC I)の役職と支援組織を創設した。情報担当副司令官(DC I)組織は、インテリジェンス用兵機能(intelligence warfighting function)および情報用兵機能(information warfighting function)と、データおよび通信機能を1つの組織に統合するなど、さまざまな変更を加えている[4]。当初から今日まで、情報担当副司令官(DC I)チームは次のことに尽力してきた。
・ 情報用兵機能の制度化を支援するために、MCDP 8「情報(Information)」およびMCWP 8-10「米海兵隊作戦における情報(Information in Marine Corps Operations)」を含む新しいドクトリンを開発する。
・ 米海兵隊情報コマンド(MCIC)を設立し、スタンドイン・フォース(SIF)が作戦を行うのに必要な当局や許可にアクセスし、インテリジェンス・コミュニティ(IC)の機能を活用できるようにする。
・ 海兵遠征軍(MEF)情報グループを、駆け出しの作戦部隊から、世界中の部隊を指揮および統制できる完全に機能する司令部へと成長させる。
・ 米海兵隊エンタープライズ・ネットワークの保護、運用、防衛を行うネットワーク大隊を設立し、海兵遠征軍(MEF)と米海兵隊に世界規模のサポートを提供する。
・ サイバースペース、宇宙、および多数の従来の情報機動職業分野を1つの一貫した専門シリーズに統合して、新しい17XX情報作戦職業分野を作成する。
・ ネットワークの近代化を通じてハイブリッド・クラウドを実装し、人工知能(AI)対応のデータ中心の作戦に備える。
・ 情報技術、サイバースペース、データおよびAIの民間労働力に質の高い訓練、教育、経験を提供するために情報開発研究所を設立する。
上記のすべては、次に何が起こるかに必要な基盤である。
2023年8月、スミス(Smith)将軍は、米海兵隊の継続的な進化というビジョンを支える上で、情報が重要な役割を果たすことを確認する指針を示した。さらに、スミス(Smith)総司令官の指針は、戦いの性質(character of warfare)における根本的な変化を認識し、何よりも米海兵隊員が依然としてその中心に据えられていることを示した。ジョン・ボイド(John Boyd)大佐のシンプルながらも長年の実績を持つ「人、アイデア、物、この順番で」という知恵に呼応するように、米海兵隊員は依然として我々の強さと優位性の究極の源泉である。
戦い(warfare)が人間の意志の争いである限り、MCDP 1「用兵(Warfighting)」で論じられた米海兵隊の戦闘哲学(warfighting philosophy)に対するボイド(Boyd)の影響は、依然として我々を米海兵隊員の創造性と創意工夫を受け入れ、力を与え、信頼するよう駆り立てている。総司令官と情報担当副司令官(DC I)はこれを認識し、常に米海兵隊員を最優先する。我々は米海兵隊員に焦点を当て、現在利用可能なデータ、情報、そして最先端技術を提供することで、彼らの創造性を高めていく。米海兵隊員に力を与え、信頼することで、我々はあらゆる敵対者から差別化される。それが我々の競争力の源である。我々の責務は、米海兵隊員に21世紀の能力をもって力を与え、信頼を寄せてもらうことである。そうすることで、21世紀の会戦に挑み、勝利することができるのである。
この方向への取り組みを加速させるため、総司令官は情報担当副司令官(DC I)チームに、米海兵隊における情報に関するトップレベルのビジョン策定を指示した。この任務では、情報担当副司令官(DC I)ポートフォリオ全体にわたるデータ、情報、通信、インテリジェンス、サイバースペース、宇宙、電磁スペクトラム、そしてその他すべての情報に基づく能力と機能が、米海兵隊員をどのように力を与え、統合用兵(joint warfighting)に一体となって貢献するかについて、統一されたビジョンを提示する必要がある。これは決して容易なことではない。このビジョンを構築するには、過去数年間のフォース・デザインで学んだことを応用し、次の段階である戦力開発を推進する必要がある。
これまでに何を学んだか?
米海兵隊は、物理的な機動と支援兵科を組み合わせた単純な戦場の見方から、全ドメイン諸兵科連合というより洗練された見方へと移行しつつある。近年この移行において大きな進歩を遂げてきたが、MAGTF用兵演習(Warfighting Exercises)の傾向報告は、まだやるべきことが残っていることを示している[5]。我々が直面している主な課題は、敵対者が我々に向かってキル・ウェブを張るのを防ぎながら、複雑なキル・ウェブを閉じる能力をどのように構築し維持するかである。この課題に対処するには、米海兵隊員が情報の役割と、その取組みを可能にし支援するためにデータを使用する方法を理解できるように支援する必要がある。もう1つの主要な課題は、米海兵隊員が常にナラティブの会戦(a narrative battle)に参加していることを理解できるように支援し、その会戦に勝利するために必要なツールを提供することである。これらは我々が解決できる、そして解決するつもりである情報の問題である。
上記を達成するためには、米海兵隊はいくつかの人的資本問題を解決する必要がある。ボイド(Boyd)の「人、アイデア、モノ、この順番で」という哲学を実践に移すには、まず米海兵隊全体の教育訓練問題に取り組む必要がある。すべての米海兵隊員、特に指揮官は、データ中心の作戦における自らの役割と、用兵機能(warfighting functions)全体にわたって情報を統合・活用する方法をより深く理解する必要がある。次に、米海兵隊は情報関連分野で勤務する米海兵隊員と民間人の育成と維持に関する問題を解決する必要がある。これらの問題は、需要が高く密度の低い必須スキルへの専門性の欠如から、キャリアの停滞や非効率的な活用まで多岐にわたる。さらに、米海兵隊はインテリジェンス職業分野における十分な人員の育成と維持においても同様の問題を克服する必要がある。
米海兵隊は、データを最大限に活用して人々に能力を与え、意思決定を支援していない。データは米海兵隊のあらゆる機能、任務、活動の根幹を成すものであるが、米海兵隊のデータは現状、効果的な活用や意思決定を可能にするような形で整理、構造化、管理、処理、提示されていない。このデータ活用の不備により、米海兵隊はデータ、インテリジェンス、通信のニーズの間で絶え間ないトレードオフを繰り返しながら、情報に基づく優位性を追求しなければならない状況に陥っている。これらの分野とサイバースペース、宇宙空間を統合した単一の統一のコンセプトとして「情報」を最終的に同期させるまで、米海兵隊は依然として不十分なままである。
インテリジェンスに関しては、部隊編成に関する分析、ウォーゲーム、演習の結果は、現代の作戦環境の観察結果と一致しており、偵察・対偵察(RXR)の闘いでの勝利が極めて重要である。米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)は、環境の変化を予測し、その先手を打つために、近代化を継続する必要がある。そうすることで、米海兵隊は統合競争(joint competing)と統合用兵(joint warfighting)の一環として偵察・対偵察(RXR)の闘いに勝利することができる。米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)は、大規模で多分野にわたるデータ・セットとインテリジェンス・フィードを迅速に解釈できるデータおよび情報技術、そして米海兵隊全体、統合部隊、インテリジェンス・コミュニティ(IC)とのソフトウェア定義による双方向接続を組み込む必要がある。
高度に接続された双方向データ中心の環境において、インテリジェンス・コミュニティ(IC)の卓越した機能は世界中で瞬時に利用可能となる。調査結果は、この接続性を活用し、スタンドイン・フォース(SIF)を統合部隊の目と耳としてだけでなく、インテリジェンス・コミュニティ(IC)としても機能させる必要があることを示している。このニーズに応えるため、米海兵隊は米海兵隊情報コマンド(MCIC)を設立し、スタンドイン・フォース(SIF)をインテリジェンス・コミュニティ(IC)、そしてサイバー軍(CYBERCOM)や宇宙軍(SPACECOM)といった世界中の戦闘軍指揮官(combatant commanders)とより緊密に連携させた。この連携は、スタンドイン・フォース(SIF)と戦闘軍指揮官間の相互支援関係を決定的に可能にし、データ、権限、許可の交換、配置とアクセス情報を用いた効果の創出を可能にする。
我々は、最近の出来事と米海兵隊の集団学習キャンペーン(collective campaign of learning)から多くのことを学んだ。我々は、学んだことを活かし、更なる向上に努めなければならない。
情報に関する統一ビジョンに向けて
情報担当副司令官(DC I)ポートフォリオ内の多様な機能と能力は、米海兵隊員と米海兵隊が何らかの情報に基づく優位性や効果を獲得または活用することを支援するために存在する。情報に関する統一ビジョンを策定するという総司令官のタスクは、情報に基づく優位性や効果を獲得し活用するために、米海兵隊を組織、訓練、装備し、情報と技術の力を活用できるようにすることである。これが「スマートに闘う(Fighting Smart)」という統一ビジョンの基盤であり、このビジョンはMCDP 1「用兵(Warfighting)」の最後の文章から直接引用されている。「機動戦(maneuver warfare)とは、戦争における、そして戦争について考える方法であり、我々のあらゆる行動を形作るものである・・[それは]最小限のコストで敵に対して最大の決定的効果を生み出すための哲学であり、「スマートに闘う(Fighting Smart)」ための哲学である」[6]。
21世紀において、米海兵隊員はどのようにスマートに闘うのだろうか?米海兵隊員はどのように洞察力を養い、想像力を活用し、革新によって混乱した環境に適応するのだろうか?米海兵隊はデータと情報を戦術的優位性と戦闘力に変換するための最先端技術をどのように提供しているのだろうか?米海兵隊員はどのようにこれらの優位性を活かし、敵対者を出し抜き(out-think)、競争で勝利し(out-compete)、闘い抜く(out-fight)のだろうか?これらは、「スマートに闘う(Fighting Smart)」が答える根本的な問いの一部である。
このビジョンを実現し、これらの基本的な疑問に答えるために、米海兵隊は、総司令官の優先事項である人材、即応性、近代化に関連するギャップを埋める必要がある。人材と即応性に関しては、個々の米海兵隊員が情報の処理方法とそれを効果的に使用するための役割を理解できるように教育および訓練し、次に、スキルと利用可能な技術を最大限に活用できるように人材を職務に適合させる必要がある。これには、個々の才能を現実的で困難な部隊訓練に統合することが含まれる。この組み合わせにより、データ中心の作戦アプローチが可能になる。あらゆるレベルの指揮官と米海兵隊員は、敵対者よりも優れた迅速な意思決定を行う能力と、用兵上の優位性(warfighting advantages)を維持または向上させる方法で敵対者への情報を操作または拒否する能力から恩恵を受ける。
近代化に関しては、先進技術を用いて利用可能なあらゆるデータを統合し、関連性と信頼性のある情報をタイムリーに伝達する能力を向上させる必要がある。これにより、分散作戦(distributed operations)が可能になり、近代化された米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)を通じた全ドメイン偵察・対偵察(RXR)も可能になる。さらに、利用可能なあらゆるデータを統合することで、同盟国、パートナー、そして統合部隊を全ドメイン諸兵科連合に統合し、統合および統合キル・ウェブを閉鎖することが可能になり、米海兵隊が敵対者に作り出せる潜在的なジレンマを大幅に高めることができる。これを実現するために、米海兵隊は信号インテリジェンス(SIGINT)、電磁スペクトラム作戦、サイバースペース作戦を統合した組織コンセプトとフォーメーションを開発する必要がある。
戦場でデータを活用して優位に立つためには、米海兵隊は、必要時にソフトウェアアプリケーションとデータソリューションを迅速に構築することで適応力を発揮することが有利に働いた最近の事例から学ぶ必要がある。第18空挺軍団は、熟練したソフトウェア開発者(software coders)とエンジニア(software engineers)のチームを配備し、進化する任務と指揮官の情報ニーズに対応するデータソリューションを動的に構築することの有効性を実証した好例である。我々の海兵遠征軍(MEF)の指揮官も同様の能力を備えるべきである。
スマートに闘う機関に向けてへ
軍種のリーダーと参謀は、組織の運営を支援するために近代化を進めることで、スマートに闘うことができる。あらゆるレベルのリーダーと参謀は、効果的な活用と意思決定を可能にする方法でデータを整理、構造化、管理、処理する能力から恩恵を受ける。組織レベルでデータ中心の作戦を近代化することで、制度の計画策定、フォース・デザインと戦力開発、調達、予算編成、採用と維持、配置、訓練と教育、戦力の創出と運用、態勢決定、戦略的コミュニケーション、そして配備と兵站計画策定が大幅に改善される。
「スマートに闘う(Fighting Smart)」はすべての米海兵隊員に適用され、情報環境の即時性と相互接続性を強調している。民間の米海兵隊員や支援業者を含むすべての人々の行動と発言の可視性と潜在的な影響を強調している。統一された情報ビジョンを実現するには、情報規律の実践、すなわちプロ意識の維持と、あらゆる発言と行動が世界的に可視化されているという認識の維持が不可欠である。この認識は、米海兵隊の評判を伝えるナラティブ(reputational narrative)を高めることにも、阻害することにもなり、国内外の公衆の知覚(public perception)に影響を与える[7]。
米海兵隊の進化を継続するには、防衛調達の実施方法にも変革が必要である。米海兵隊は、作戦指揮官が作戦と維持整備(O&M)予算を活用して能力を獲得するなど、より迅速な対応の必要性を認識している。外部指導者や議会は長年にわたり変革を求めてきた。米海兵隊システム司令部は最近、調達を強化するために再編されたが、依然として課題は山積している。国防革新・採用委員会は、2024年1月に発表した報告書の中で、民間部門と防衛部門の最先端技術を迅速に導入することが喫緊の必要性であると強調している。そうすることで、戦闘員に影響力の大きいソリューションをよりタイムリーに提供できるようになる[8]。
そのため、我々の認定事業(programs of record)内の根本的な焦点の転換が必要となり、ハードウェアよりもソフトウェア要件を重視することになる。また、この転換により、迅速なソフトウェアの修正と更新を可能にするプログラムも必要となる。これにより、兵士たちはデータの融合と相関分析によって意思決定、行動、そして成果を導き出し、競争優位性を維持できるようになる。米海兵隊ソフトウェア・ファクトリ(MCSWF)のような組織は、迅速なソフトウェア開発を支援し、実現することを目指している。「スマートに闘う(Fighting Smart)」は、要件開発と調達、そして米艦隊海兵部隊(FMF)へのソフトウェア開発支援の提供において、米海兵隊を重要な改革へと導くために必要な行動を特定する。
我々はどこへ向かっているのか?
「スマートに闘う(Fighting Smart)」とは、データと情報を戦闘力へと転換する作戦の方法であり、米海兵隊員が敵対者よりも迅速に、より良い意思決定を下せるようにすると同時に、データを全ドメイン指揮・統制と諸兵科連合の効率性を高める資産として活用する。この作戦方法のすべての優位性を得るために、米海兵隊は隊員に対し、その構築方法と維持方法について教育と訓練を行う必要がある。あらゆる作戦アプローチは、それを機能させるために熟練した人材を必要としており、「スマートに闘う(Fighting Smart)」も例外ではない。米海兵隊員は、データを最大限に活用して効果的に作戦する方法を知らなければならない。
「スマートに闘う(Fighting Smart)」は、ほとんどの米海兵隊員にとって馴染み深いものとなるだろう。過去数年間に策定された他の主要な軍種レベルの取り組み(例:人材管理)と同様に読めるだろう。しかし、重要な違いは、「スマートに闘う(Fighting Smart)」がこれらの取り組み、特に前述の総司令官の3つの主要優先事項と関連し、それらを可能にするという点である。さらに、「スマートに闘う(Fighting Smart)」は、特定の重点分野において、具体的な行動と更なる検討が必要な領域を定める。現在の草案では、これらの領域には、人材の動員、データ中心性の実現、米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)の近代化、そして21世紀の諸兵科の実現が含まれている。「スマートに闘う(Fighting Smart)」は2024年6月に公表される予定である。
結論
「スマートに闘う(Fighting Smart)」は、21世紀の諸兵科連合にとって、伝統的なドメインを超えて宇宙、サイバー空間、電磁スペクトラム、そして情報環境を含む、拡大する機会を意味する。マルチドメインからの収束効果を体現し、優位性と成果を生み出す。ボイド(Boyd)の哲学を真摯に受け止め、データと技術によって力を与えられた人々とそのアイデアこそが、「スマートに闘う(Fighting Smart)」の中心にある。最終的に米海兵隊の競争力を維持するのは、技術ではなく、米海兵隊員である。将来の成功には、米海兵隊の関連分野における人工知能(AI)/機械学習(ML)訓練を含む、データ・リテラシーの高い訓練が不可欠である。艦隊海兵隊とその支援組織は、意思決定を向上させるための専門的なスキルセットを備えた人材を必要としている。
データによって力を与えられた人材は、米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)の近代化においても中心的な役割を果たす。近代化と統合部隊の妥当性確保には、米海兵隊が競争と紛争の両面において情報収集・伝達部隊として機能し、日々情報と影響力を求めて戦うことが求められる。米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)の近代化は、キル・ウェブの封鎖に不可欠であり、21世紀の統合兵科を可能にする。近代化された米海兵隊インテリジェンス・監視・偵察事業(MCISR-E)は、意思決定における優位性と統合部隊のレジリエンス(復元性)の創出にも役立ち、ナラティブをめぐる会戦(the battle for narratives)における理解と競争を支援する。
上記を達成するには、データで人々に力を与え、必要な教育と訓練を提供し、組織がデータ中心の能力を迅速に提供できるようにすることが不可欠である。「スマートに闘う(Fighting Smart)」は、技術主導で高度に接続された世界における米海兵隊の進化の青写真となり、現代の課題に対応し、戦闘員の作戦リスクを軽減するための組織的適応性の必要性に取り組んでいる。
ノート
[1] ジョン・アンタル、「第一次世界大戦の勝利は主に無人システムによってもたらされた、ンゴルノ・クラバフ戦争から得られる10の教訓」 Madscriblog、2021年4月1日、https://madsciblog.tradoc.army.mil/317-top-attack-lessons-learned-from-the-second-nagorno-karabakh-war
[2] 同上
[3] 人工知能に関する国家安全保障委員会、 最終報告書:人工知能に関する国家安全保障委員会(ワシントン D.C.:2021 年)
[4] 米海兵隊本部、 米海兵隊広報5400「情報担当副司令官の設置」(ワシントンD.C.:2017年)。
[5] 海兵航空地上任務部隊訓練司令部、 海兵航空地上戦闘センター、MAGTF戦闘演習2-23最終演習報告書(トゥエンティナインパームス:2023年)
[6] 米海兵隊本部、 MCDP 1、戦闘(ワシントン D.C.: 1997)
[7] 米海兵隊本部、 MCDP 8、情報(ワシントン D.C.:2022年)
[8] 大西洋評議会、スコウクロフト戦略安全保障センター、 防衛技術革新・採用委員会、最終報告書(ワシントン D.C.: 2024年)