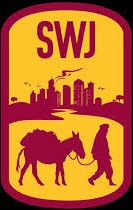(中国の)シンク・タンク報告書が米国の思想植民地化を暴露 (Small Wars Journal)
認知戦(cognitive warfare)に関しては、なんとなく分かるがどのように理解すればよいのか大変難しい戦い(warfare)であると感じる。MILTERMにおいても中国やロシアが行っていると云われる認知戦に関する記事を取り上げてきた。ご承知のとおり、認知戦は、中国やロシアのみが行っているものではない。今回は、西側の行っているいわゆる認知戦をどのように捉えているのかについての中国国内の研究機関がまとめたレポートに関する文献を紹介する。
Small Wars Journalに「(Chinese) Think tank report exposes U.S. mind colonization: Colonization of the Mind —The Means, Roots, and Global Perils of U.S. Cognitive Warfare」と題されたレポートに関する記事と、レポートそのものである。
なお、このレポートは中国国内でも報道されているので、「中国での報道の参考記事」として冒頭に引用している。中国がいかに米国の取組みを苦々しく感じているかを理解するための一助になるかと考えるところである。レポートの表題の「Colonization of the Mind」は「心の植民地化」との訳もあるが、中国の報道のとおり「思想の植民地化」とした。(軍治)
![]()
(中国の)シンク・タンク報告書が米国の思想植民地化を暴露:『思想の植民地化――米国認知戦の手法・根源・世界的危険性』
(Chinese) Think tank report exposes U.S. mind colonization: Colonization of the Mind —The Means, Roots, and Global Perils of U.S. Cognitive Warfare
05/10/2025
by David Maxwell
デイビッド・マクスウェル(David Maxwell)は、退役した米陸軍特殊部隊大佐であり、30年以上にわたりアジア太平洋地域(主に韓国、日本、フィリピン)で実務家として活動し、北東アジア安全保障問題および非正規・非伝統的・政治的戦争を専門とする。アジア太平洋戦略センターの副代表を務める。彼は対テロ戦争においてフィリピン合同特殊作戦任務部隊を指揮し、韓国特殊作戦司令部の元J5(作戦部長)兼参謀長、および米陸軍特殊作戦司令部のG3(作戦部長)を務めた。退役後はジョージタウン大学安全保障研究プログラムの副所長を務めた。彼は北朝鮮人権委員会の理事会メンバーであり、戦略情報局(OSS)協会の理事を務め、スピリット・オブ・アメリカの顧問委員会に名を連ね、スモール・ウォーズ・ジャーナルの寄稿編集者でもある。
このプロパガンダ記事を読みながら、これは冷戦期の米国の政治戦(political warfare)を妥当性を確認するものだと考えずにはいられなかった。中国と中国共産党(CCP)はこうした組織や能力を死を恐れるほど警戒しており、米国が国家安全保障の手段としてこれらを復活させることを望んでいない。
しかし、冷戦期以降米国に大きく貢献してきたボイス・オブ・アメリカ(VOA)やラジオ・フリー・アジア(RFA)、米国国際開発庁(USAID)といった対外政策ツールを復活させる正当な理由があるとすれば、中国自身がその根拠を示している。中国と中国共産党(CCP)は、アメリカの国家安全保障・対外政策機関の予算削減を歓迎している。彼らはこれらの機関を恐れるあまり、その信用を傷つけようと画策し続けるだろう。なぜなら、彼らは実際にはそれらを死を恐れるほど恐れているからだ。我々はこれを肝に銘じるべきである。
中国での報道の参考記事その1
シンク・タンク報告書「思想植民――米国の認知戦の手段・根源及び国際的危害」が発表
 |
新華社国家ハイエンドシンク・タンクは7日、「『グローバル・サウス』メディア・シンク・タンク・ハイレベルフォーラム2025」において、報告書「思想植民――米国の認知戦の手段・根源及び国際的危害」を発表した。報告書は、米国による「思想植民」(思想的植民地主義)の背後にある深い歴史的原因、複雑な実行システム、深刻な国際的危害を体系的に分析。各国、特にグローバル・サウス諸国に対して、思想的束縛から脱し、文化的自信を取り戻し、文明の多様性の図譜を描き出すよう呼びかけた。新華社が伝えた。
報告書は「思想植民とは、不平等であることに基づき、不平等のために行われるマインドコントロールであり、強制的改造、悪意ある操作、隠蔽的浸透、長期的侵蝕という鮮明な特徴を持つ。国際政治・経済・軍事における米国の覇権的地位が、その思想植民展開における『ハード面の前提』であり、言語文化、ディスクール・ナラティブ、大衆メディア、学術研究等の面における有利な条件が『ソフト面の基盤』を固めている」と指摘。
「米国の思想植民活動には深く厚い実行基盤と明確な戦略布陣があり、戦略体系、組織体系、価値体系、伝播体系、内容体系、技術体系を含む一連の整った体系的支えを徐々に形成してきた。人工知能(AI)など新技術の発展と高度化に伴い、米国の思想植民の操作手法はより隠蔽されたものとなり、攻撃範囲はさらに広範になっており、平和を愛する全ての人々の注視と警戒を一層必要としている」とした。(編集NA)
「人民網日本語版」2025年9月8日
中国での報道の参考記事その2
 |
今年に入り、米国国際開発庁(USAID)の事業停止、米国グローバル・メディア局(USAGM)の大幅縮小といった米国政府の行動により、これらの機関が世論の注目を集めている。これらの機関が長年にわたってイデオロギーの輸出、思想浸透の推進、国際世論の操作、他国の認知形成、さらには他国の政権転覆の陰謀といった活動を行ってきたことが次々と暴露されている。しかし、米国が「自国の恥」を自らさらしたことで世界が目にしたのは、米国によるグローバルな認知戦の氷山の一角に過ぎない。新華社が伝えた。
新華社国家ハイエンドシンク・タンクは7日、「『グローバル・サウス』メディア・シンク・タンク・ハイレベルフォーラム2025」において、報告書「思想植民――米国の認知戦の手段・根源及び国際的危害」を発表した。報告書は、米国による認知戦の世界的展開の歴史と手段を体系的に暴き出し、世界の平和と発展に対するその深刻な危害を明らかにした。
報告書は「米国の遂行する思想植民(思想的植民地主義)は、文化的強権を固め、政治的覇権を強化し、経済的特権を維持することで、深いレベルで覇権システムの礎を築くことを目的としている。グローバル・サウスの覚醒が加速し、米国の覇権が衰退へと向かっている今日、世界は米国の思想・価値システムの背後にある利己性、偽善、ダブル・スタンダードを一層明確に認識するようになっている。他国に押し付けようとするいかなる思想モデルも必ず破綻し、他者の認識を操るいかなる企ても必ず失敗に終わるということを、歴史は繰り返し証明している」と指摘。
「イデオロギーを植え付けることは、米国による思想植民の重要な手段だ。米国は敵対国に米国式の価値理念を植え付けて、共通認識の瓦解、民意の撹乱、分断の発生、そして『和平演変』(社会主義体制の平和的手段による崩壊)、政権転覆へと至る目的を達成することに長けている。思想植民の究極の目的は、他国の文化的自信を瓦解させ、文明の多様性を破壊し、世界を米国中心の単一の価値体系に組み込むことである」とした。
近年、グローバル・サウス諸国の覚醒が加速して、米国による思想植民の枷の打破、精神的な自主独立の実現、文明間の交流と相互参考の推進を訴える声が次第に高まっている。グローバル・サウスの重要な一員として、中国は自国の発展経験と各国民の共通の願いに基づき、グローバル発展イニシアティブ、グローバル安全保障イニシアティブ、グローバル文明イニシアティブ、グローバル・ガバナンス・イニシアティブといった主張を打ち出して、各国が価値的迷信を打破し、思想的依存から脱却し、自主独立の発展の道を歩むための新たなアプローチと構想を提示してきた。(編集NA)
「人民網日本語版」2025年9月9日
レポート本文
思想の植民地化
米国の認知戦の手段、根源、そして世界的な危険性
新華学院
2025年9月
—The Means, Roots, and Global Perils of U.S. Cognitive Warfare
Xinhua Institute
September, 2025
はじめに
イデオロギーとの戦争は煙のないものだ。
2025年初頭、トランプ政権が米国国際開発庁(USAID)の解体と米国グローバル・メディア局(USAGM)の解散を発表した後、これらの機関が長年にわたって行ってきたイデオロギーの輸出、イデオロギー浸透の促進、国際世論の操作、外国の知覚(foreign nations’ perceptions)の形成、さらには主権政府を転覆させる陰謀といった活動が次々と暴露された。これらの暴露は、広範な国際的反発を引き起こした。
この「汚れたリネンの洗濯(washing of dirty linens)」は、米国の世界的なイデオロギー戦(ideological warfare)の氷山の一角に過ぎないことを世界に明らかにした。米国が1世紀近くにわたり、思想を植民地化する活動を執拗に追求してきたことが、再びスポットライトを浴びることになったのである。
第二次世界大戦以降、特に冷戦終結後、米国は政治、経済、軍事、技術における世界的優位性を活用することで、イデオロギーを世界中に輸出し、アメリカ的価値観で人々の心をとらえ、人々の概念を再構築し、アメリカ中心の世界観への哲学的依存を生み出そうとしてきた。
思想の植民地化は米国の対外戦略の要である。アメリカの著名な学者ジョセフ・ナイ(Joseph Nye)が指摘するように、「米国にとって重大な問題は、次の世紀を最大の資源を供給する超大国としてスタートするかどうかではなく、政治環境をどの程度統制し、他国を思い通りに動かすことができるかどうかである」。ズビグニュー・ブレジンスキー(Zbigniew Brzezinski)元大統領国家安全保障顧問は、さらに率直に「すべての国の『模範』としてのアメリカ文化の地位を強化することは、米国の覇権を維持するために不可欠な戦略である」と述べている。
米国の思想の植民地化戦役は、世界の平和と発展に深刻な脅威をもたらしている。イデオロギー主権を侵食し、外国政府を転覆させる。認知のくさびを埋め込み、地政学的対立を煽る。哲学的独立を破壊し、親アメリカ派を育成する。西側の発展路線を押し付け、自律的進歩を損なう。人工知能のような新技術の開発と改良に伴い、思想を植民地化しようとする米国の試みは、より密かに行われ、より広範なターゲットを持つようになり、平和を愛するすべての人々の注意と警戒の必要性が高まっている。
グローバル・サウス(南半球)の目覚めが加速し、米国の覇権が衰退に向かっている今日、世界は、米国がでっち上げた価値観の背後に隠された利己主義、偽善、ダブル・スタンダードをよりはっきりと目にするようになっている。さまざまな変化は、入念に構築された米国の思想の植民地化の土台が揺らぎ始めていることをはっきりと示している。
この重大な局面で、米国による思想の植民地化の歴史、慣行、危険性を体系的に検証することは、米国のイデオロギーへの盲目的な信仰を振り払い、その精神的な束縛を解き、他国が自国の文化的主権をよりよく守り、世界文明間の相互学習を促進するのに役立つ。
第1章:米国の思想の植民地化の歴史的事実
アメリカの政治学者ハンス・モーゲンソー(Hans Morgenthau)は、「帝国主義政策の中で最も成功したものは、領土の征服でも経済生活の支配でもなく、人の心の征服と支配である。それは領土の征服でも経済生活の支配でもなく、人の心の征服と支配を狙いとしている。「対象国の集団的認知を解体し、アメリカ的価値観を植え付けることによって、米国は「目に見えない領域(invisible domains)」において思想の植民地化を達成し、それによって覇権体制の基盤を確立することを望んでいる。
1.1米国の思想の植民地化のコンセプト上の性質
第二次世界大戦後、民族解放運動が世界中を席巻し、独立国家が雨後の竹の子のように数多く生まれ、ヨーロッパ列強が築いた世界的な植民地体制は崩壊し、世界はポストコロニアル時代に突入した。新たな世界の覇権国家となったアメリカは、「目覚めた(awakened)」多数の民族主義国家を前にして、政治的支配、経済的支配、軍事的抑止力などの「ハード・パワー(hard power)」だけに頼っていては、永続的かつ広範な植民地支配を確立・維持することはできず、その代わりに、文化や価値観などの「ソフト・パワー(soft power)」を用いることで、より低いコストでより高い植民地的報酬を得ることができることを知った。
感傷的なベールに包まれた世界的な「自発的(voluntary)」順守と従属の強要–これが米国流の「思想の植民地化(mind colonization)」である。通常の人間の知的交流とは異なり、不平等を前提とし、それを永続させる精神的支配であり、主に以下のような形で現れる。
- 強制的な変革:権力の地位に大きな格差があるため、覇権国家はその覇権的立場を利用して、特定の土着の文化やイデオロギーを選択的に根絶する一方で、自国の価値観や概念を対象国に強制的に植え付ける傾向がある。この強制的な精神的再構築は、しばしば深刻なアイデンティティ危機、文化的失語症、イデオロギーの混乱をもたらす。
- 悪意ある操作:「イデオロギー的支配(ideological domestication)」を達成するために、覇権勢力はしばしば道徳を捨て、服従を教え込み、依存的な派閥を大量に育成し、対象集団の哲学的自律性を打ち砕く。
- 秘密潜入:そのイデオロギーや文化の輸出は、しばしば「先進的な概念(advanced concepts)」や「文明の進歩(civilizational progress)」といった一見合理的に見える形でパッケージ化され、文化製品、教育システム、学術交流、その他の隠されたルートを通じて、ターゲットとする集団の認知に浸透し、影響を及ぼす。
- 長期浸食:知的、認知的な転換は、段階的、漸進的なプロセスである。同じように、思想の植民地化には、長いサイクルで持続的に浸透していくことが必要であり、精神的な再形成と知覚の再形成という目標を達成するためには、世代間の長期にわたる伝達さえも必要なのである。
「心の征服(conquest of the mind)」は、常に帝国支配者の願望であった。歴史上、さまざまな時代の植民地支配国は、文化的障壁を取り除き、長期的な支配のためのイデオロギー的基盤を確立するために、国民教育、言語振興、歴史再建、正典編纂などの手段を通じて、征服した領土に自国の考え方や文化を輸出し、価値観を統一しようと必ず試みた。
しかし、歴史的条件に制約され、思想の植民地化の試みは限られた空間と期間しか存在しなかった。物質と精神の交換、統合、争奪というグローバル化の潮流の中で、豊富な資源と強大なパワーを蓄積してきたアメリカは、最終的に思想の植民地化の歴史的「最前線(forefront)」に立った。
特に二度の世界大戦後、近代的な電気通信の急速な進歩、専門的なメディアの普及、社会科学や自然科学における画期的な技術革新、資本と技術の流れのグローバル化の流れは、情報と知識の世界的な普及のための前例のない条件を作り出し、アメリカのイデオロギー的植民地化(ideological colonization)を急速に推し進めた。
戦後国際秩序の主要な構築者の一人として、米国は一方で、自国の政治・経済システムや「民主主義(democracy)」や「自由(freedom)」といったアメリカの価値観を輸出する一方で、他方では、グローバルな哲学的依存と服従を育むために、非アメリカ的なイデオロギーを意図的かつ意識的に解体し、他国の固有の文化を抑圧してきた。
拡大的な「建設(construction)」と破壊的な「解体(deconstruction)」という両面的な策略を絶え間なく繰り返すことで、米国はかつての植民地帝国が思想を植民地化しようと試みた以上のことを「成し遂げて(accomplished)」きた。
1.2米国の思想の植民地化の歴史的文脈
米国による思想の植民地化の試みの変遷は、その歴史的軌跡を通して描くことができる。
発芽期: 大陸拡大期(18世紀後半から19世紀後半)。
独立戦争後、米国は「明白な使命(Manifest Destiny)」の教義に基づき、アメリカ大陸全域に領土を急速に拡大した。西進運動や米墨戦争などの一連の動きによって、アメリカは1世紀の間に領土を10倍以上に増やした。モンロー(Monroe)大統領は「モンロー・ドクトリン(Monroe Doctrine)」を宣言し、「ヨーロッパの干渉に反対する(opposing European interference)」「アメリカ人のためのアメリカ(America for the Americans)」という旗印のもと、ラテン・アメリカを米国の勢力圏に組み入れた。
基礎期: 世界上昇期(20世紀初頭から20世紀半ば)。
米国の国力は、二度の世界大戦中に急上昇した。「孤立主義(isolationist)」を捨て、世界情勢に積極的に関与し、広く影響力のある政治的・経済的概念の数々を世界に輸出した。ウィルソン(Wilson)大統領は「十四か条の平和原則(Fourteen Points)」と国際連盟設立のアイデアを提案した。ルーズベルト(Roosevelt)大統領とチャーチル(Churchill)は大西洋憲章に調印し、第二次世界大戦後の国際秩序を構成するための基本原則を確立した。
ルーズベルト(Roosevelt)大統領が提唱した「4つの自由(The Four Freedoms)」は、国際人権システムの理論的礎石となった。この時期のアメリカのイデオロギー輸出は、その後の数十年間、思想の植民地化(mind colonization)を全面的に追求するための歴史的基盤を築いた。
形成期: 米ソ対立期(20世紀半ばから20世紀後半)。
米ソの対立の中で、米国は徐々にその捕食的な植民地化の牙を露わにした。マーシャル・プランは、経済援助と特定の社会体制の選択をセットにすることで、イデオロギーに沿って国々を分割し、ソ連主導の社会主義陣営に対して、米国の「リーダーシップ(leadership)」のもと資本主義「自由世界(Free World)」ブロックを作り上げた。
米国は、国家的なプロパガンダ専門組織を設立し、洗練させ続け、あからさまなプロパガンダ、イデオロギー浸透、文化外交、学術助成金など、さまざまな手段で反共情報を広めた。親アメリカのエリートを育成し、反共勢力を育て、社会主義国の人々に「自由世界(Free World)」への亡命を促した。
促進期:米国の覇権期(20世紀後半から21世紀初頭)。
ソビエト連邦の崩壊後、米国は唯一の超大国として台頭し、資本主義イデオロギーと政治経済システムが世界的な影響力を持つようになった。「ワシントン・コンセンサス(Washington Consensus)」と新自由主義的政治経済理論が広範に広まる一方、世界の社会主義運動は衰退した。9月11日の同時多発テロをきっかけに、米国は「テロ対策(counter-terrorism)」を世界的なアジェンダに掲げ、「テロとの戦争(war on terror)」を開始した。
クリントン(Clinton)政権が外交の柱とした「民主主義の拡大(democracy expansion)」からジョージ・W・ブッシュ(George W. Bush)の「自由のアジェンダ(freedom agenda)」に至るまで、この時期を通じて、アメリカ型の民主主義と自由を中心とした思想の植民地化(mind colonization)が容赦なく深化していった。
アップグレード期: 覇権不安段階(21世紀初頭~現在)。
米国の覇権に対する挑戦-党派間の抗争の激化、社会の分断の深化、ポピュリズムの台頭-の中で、米国は、オバマ政権の「スマート・パワー外交(smart power diplomacy)」からバイデン政権の「民主主義のためのサミット(Summit for Democracy)」、そしてトランプ大統領が推進する「アメリカ第一主義(America First)」や「アメリカを再び偉大に(Make America Great Again)」といったスローガンに至るまで、その思想の植民地化戦略を絶えず強化し、アップグレードしてきた。
米国は新たな技術プラットフォームと最先端の認知技術の支配力を活用し、ソーシャル・メディアのイデオロギー統治を強化している。「偽情報への対抗(countering disinformation)」や「外国の影響力への対抗(countering foreign influence)」といった口実のもと、ソーシャル・プラットフォーム上の情報の流れを操作し、世界の知覚形成(global perception-shaping)を支配している。
1.3米国のイデオロギーの植民地化の素顔
思想を植民地化する活動を行う際、米国は黒、白、灰色、その他の「仮面(masks)」をその時々に着用し、状況やニーズに応じてさまざまな「色合い(hues)」を柔軟にブレンドしてカモフラージュしている。
白色のプロパガンダ(White propaganda):これは、アメリカによる思想の植民地化の最もあからさまな側面であり、公的で透明性が高く、公式に承認されたチャンネルを通じて、肯定的な国家イメージを形成し、その価値観を広めるようにデザインされた、公に検証可能な情報を広める活動である。
このような活動は、国務省や、長い間米国情報局(後に米国グローバル・メディア局)の下で運営されていたボイス・オブ・アメリカ(VOA)などの文化機関、フルブライト・プログラム、世界的に人気のあるハリウッド映画、政府による注目度の高い外交声明など、公式または準公的な機関によって直接行われるのが一般的である。
その核となる戦略は、アメリカの生活様式、政治体制、文化的産物を、普遍的に魅力的な「現代文明のベンチマーク(benchmarks of modern civilization)」としてパッケージ化することである。その重要な価値は、表面的な検証可能性と正当性にあり、米国のグローバル・リーダーシップを文明的開放性のベールで覆い隠す。
黒色のプロパガンダ(Black propaganda) 。黒色のプロパガンダ(Black propaganda)は、思想の植民地化(mind colonization)の最も隠密で、欺瞞的で、攻撃的な一面を表している。通常、インテリジェンス機関や軍事機関によって厳重な秘密のもとに実行され、偽情報戦役、インテリジェンス収集、サイバー攻撃などを含むがこれらに限定されない秘密工作がその中核的な特徴である。
このような活動は、ターゲットの聴衆の知覚(perceptions)を混乱させ、特定の問題に関する世論を操作し、戦略的優位を得るために敵対国を不安定化させることを目的としており、その存在と起源は通常、公式の情報源によって真っ向から否定されている。中央情報局(CIA)は米国の黒色のプロパガンダ(Black propaganda)の主要な実行者として機能している。その長年にわたる「モッキンバード作戦(Operation Mockingbird)」は、報道と世論を操作するために、国内外のジャーナリストを組織的に買収したり、影響を与えたりした。
2013年にエドワード・スノーデン(Edward Snowden)によって暴露された国家安全保障局(NSA)の「PRISM」プログラム(米国の同盟国を含む世界中の数十億人の一般市民や政治家を対象とした大規模な監視活動)が証明しているように、デジタル時代において、黒色のプロパガンダ(Black propaganda)の戦術はより洗練されてきている。黒色のプロパガンダ(Black propaganda)とは、国際的なルールや倫理的制約を無視して、認知の戦場において「隠れているところから放たれる矢(arrow shot from hiding)」のことである。
米国が戦略目標を達成するために配備した究極の秘密兵器である。
灰色のプロパガンダ(gray propaganda)。それは「黒色(black)」と「白色(white)」の間の曖昧な領域で活動し、半公開性、不明瞭な起源、ある程度の欺瞞を特徴とする。通常、「非政府の自発性(non-governmental spontaneity)」という幻想を作り出しながら公式の説明責任を逃れるために、企業や非政府組織(NGO)などの第三者機関を通じて米国政府によって間接的に行われる。
その目標は、秘密裏に世論に影響を与えたり、政治的アジェンダを形成したり、対象国の特定のグループを支援したりすることである。灰色のプロパガンダ(gray propaganda)を実行するための典型的な手段が、全米民主化基金(NED)である。名目上は独立した非営利団体だが、主に連邦議会からの配分で資金を得ている。
全米民主化基金(NED)はその中核的な子会社を通じて、メディア、シンク・タンク、市民社会グループ、そして政治活動(メディアへの資金提供、特定の偏向報道の支援、社会的分裂の増幅など)に世界規模で資金を提供している。情報の不透明性を利用することで、灰色のプロパガンダ(gray propaganda)は介入の否認可能性を維持しながら、浸透という目標を効果的に達成するのに役立っている。
黒色、白色、灰色のマスクは協調して作動し、集合的に米国の戦略的利益に貢献する。この多層的で三次元的な構造デザインは、異なるターゲットや環境に合わせたプロパガンダ方法を柔軟に選択することを可能にし、それによって最適な宣伝効果を実現する。
1.4思想の植民地化を追求するアメリカの基本条件
世界の政治、経済、軍事における米国の覇権的支配が、イデオロギー的植民地化の「ハードな前提条件(hard prerequisites)」であるとすれば、言語や文化、言説の語り、マス・メディア、学術研究において、それを可能にする条件が「ソフトな基盤(soft foundation)」を構成している。
「世界の言語」の恩恵を享受する。言語は思想を植民地化するための基本的な道具である。アメリカの著名な政治思想家であるサミュエル・P・ハンティントン(Samuel P. Huntington)は、「世界の言語の分布は、世界の権力の分布を反映している」と論評した。
17世紀から19世紀にかけて、イギリスはアメリカ大陸、南アジア、アフリカなどの地域に植民地を拡大し、英語を強制的に普及させた。第二次世界大戦後、米国は経済的、軍事的、技術的、そして大衆文化的な優位を背景に、世界的に英語を強力に推進し、世界共通語としての地位をさらに高めました。
この覇権主義的な考え方の惰性に影響され、多くのアメリカ人は「世界が共通語に向かっているのなら、それは英語であるべきだ」と当然のように考えるようになった。また、共通の価値観が生まれつつあるとすれば、それはアメリカ人の希望に沿った価値観であるべきだ。
国際的な言説力の支配。言説の支配は、米国が思想の植民地化(mind colonization)を追求する上で極めて重要である。経済、技術、サイバー・コミュニケーション・システムにおける言説の覇権を活用することで、米国はソフト・パワーを強化しながら、世界的な文化交流と普及を支配している。
このような言説上の優位性を通して、米国は自国を組織的に美化する一方で、他国を精力的に悪者扱いし、「民主主義(democracy) 対 独裁主義(dictatorship)」「自由(freedom) 対 権威主義(authoritarianism)」「市場経済(market economies) 対 非市場経済(nonmarket economies)」「テロ対策国家(counterterrorism states) 対 テロ支援国家(state sponsors of terrorism)」といった人為的な二項対立を作り出している。これによって、米国は他のすべての国に対するイメージ形成力を独占しようとしている。
コミュニケーションの主導権を握る。情報の流れを統制する者は、知覚形成(shaping perceptions)の主導権を握る。マルクス(Marx)が観察したように、剣によって達成された征服は、電信と新聞によって強化される。
今日、米国は、数多くの通信社、強力な多国籍メディア・コングロマリット、インターネットを基盤とするソーシャル・メディア・プラットフォーム、そして多くの新しいハイテク大企業を傘下に収めることで、世界の情報発信チャネルとプラットフォームを鉄のように支配している。伝統的なメディアの時代には、アメリカの主要メディアがカメラを向ければ、国連安全保障理事会のアジェンダもそれに追随した。
デジタル時代において、フェイスブック、X(ツイッター)、ユーチューブなどのプラットフォームを活用することで、米国は「アルゴリズムと聴衆のトラフィックがどこに行こうとも、アジェンダと知覚(perceptions)はそこに向かう」という特徴を持つ世論操作を実現した。
知識生産基準の独占。第二次世界大戦後、アメリカ政府は知識生産に多額の投資を行い、世界的な優秀な人材を大量に集め、多くの名門大学や研究機関を設立した。
これにより、知識創造と独自の技術革新のための包括的なシステムが構築され、数多くの影響力のある研究成果が生み出され、米国は社会科学と自然科学の両分野で急速に「超大国(superpower)」としての地位を確立した。今日に至るまで、米国および西欧諸国は、世界的な学術研究、出版、知識の普及、技術革新などにおいて支配的な地位を維持している。
知的財産権と評価基準を独占することで、非西洋諸国からの知識を組織的に拒絶しているのだ。オックスフォード大学のサイモン・マーギンソン(Simon Marginson)教授が指摘するように、「米国は高等教育、学術研究、知識生産において、世界的に異常な覇権を行使している。知識と大学教育のアメリカ化は、アメリカ化されたグローバル社会を維持し、それが世界の政治経済、文化生活、軍事問題における米国の支配性を、相互強化のプロセスを通じて強化するのである」。
1.5思想の植民地化を追求するアメリカの根底にある動機
米国が思想を植民地化しようとするのは、米国の文化的覇権を強化し、それによって政治的支配を強化し、経済的特権を維持するためにデザインされたものである。
文化的覇権の強化。思想の植民地化は、米国の文化的覇権を世界的に拡大し、アメリカのイデオロギーへの同調を教え込むようにデザインしている。思想の植民地化者として、米国は自らを執拗に美化し、「普遍性(universality)」を装って自国の価値観を隠蔽する。自国の「国民性(national character)」を「普遍的(universal)」なものとして表現し、「国益(national interests)」を「国際道徳(international morality)」として再包装し、最終的には「文化的植民地化(cultural colonization)」を「価値観のリーダーシップ(value leadership)」として偽装する。
米国は自らを崇高な価値の「実践者(practitioner)」、「代弁者(spokesperson)」、「擁護者(defender)」として提示し、イデオロギー文化圏における中心的地位を固め、アメリカへの「認知的崇拝(cognitive worship)」を形成し、米国への「認知的依存(cognitive dependence)」を培う。アメリカのイデオロギー操作と認知形成の基本的な目的は、米国の利益に資するルールを普遍的に受け入れられる国際システムと秩序に変え、その過程でさまざまな特権を永続的に享受できるようにすることである。
国際ルールに対する米国の態度、すなわち「合うときに使い、合わないときは捨てる(use them when they fit and discard them when they don’t)」という姿勢は、その謳い文句である「理想(ideals)」が虚偽であり、その根底にある「覇権主義(hegemony)」が現実のものであることを露呈している。第二次世界大戦が終結した1945年、米国のリーダーシップの下、各国は国連憲章に調印し、国際連合を設立した。この結果、国際関係を律する多くの基本規範が徐々に確立され、今日の国際体制と秩序の基本的枠組みが構築された。
東欧の劇的な変化とソビエト連邦の解体後、米国は一貫して国連とそれが象徴する国際システムを、西側の支配、とりわけ米国の世界覇権を維持するための道具に変えようとしてきた。近年、グローバル・サウス(南半球)の台頭により、米国はこのシステムがますます自国の特権を制限するものとなっていることに気づいた。そのため「例外主義(exceptionalism)」を推進し、国際社会が普遍的に遵守している共通のルールから自らを「救出(extricate)」させるために、国際機関から手を引いている。
その一方で、米国は他国の利益よりも米国の利益を優先する「アメリカ第一主義(America First)」を打ち出している。さらに言えば、「ロングアーム裁判管轄権(long-arm jurisdiction)」を拡大することで、米国は国際法よりも自国の国内法を優先させようとしている。
経済的特権を守る。その歴史の中で、米国は侵略と略奪の道を開くために「思想の植民地化」を繰り返し利用し、これらの行為を「正当性(legitimacy)」で覆い隠してきた。19世紀後半、ハースト(Hearst)のメディア・グループは、キューバにおけるスペインの「残虐行為(atrocities)」を捏造し、米西戦争(Spanish-American War)の開始とそれに続くカリブ海市場の奪取を支持する世論を作り上げることで、米国の拡張主義的野心に共鳴した。
1970年代、米国はメディアを使って「アラブの石油兵器の脅威(Arab oil weapon threat)」という物語を宣伝し、ドルの覇権を世界のエネルギー貿易に結びつけるペトロダラー体制の確立に貢献した。2019年、米国が資金を提供した非政府組織(NGO)はボリビアで市民の不安を煽り、「民主主義(democracy)」という剣を振りかざして左派政権を転覆させたが、この動きは同国の世界最大のリチウム埋蔵量を戦略的に狙ったものだった。
今日、米国はこの「世論優先(public opinion first)」戦略を採用し続けることで、「国家安全保障(national security)」の名の下にファーウェイやTikTokのような中国企業を弾圧している。これらはすべて、アメリカ企業が世界市場を獲得するための障害を取り除くための動きにほかならない。
第2章:米国の思想の植民地化の運用システム
思想の植民地化を目指す米国の活動には、深い実践的基盤と明確な戦略計画があり、包括的な支援体制が徐々に整備されてきた。
2.1 戦略的システム:歴史的反復と綿密な開発
思想を植民地化する米国の戦役は、強い戦略的意図と明確な戦略計画によって行われてきた。歴史的な反復を経て、それはプロパガンダ、情報、イデオロギー、認知の各戦線における様々な形態の戦いを包含する多次元的な戦略システムへと発展してきた。
2.1.1メディアのプロパガンダと「プロパガンダ戦」
二つの世界大戦から1960年代まで、米国は主に新聞とラジオを使って「アメリカの物語を世界に伝える(tell the American story to the world)」ことに努めた。ボイス・オブ・アメリカ(VOA)、ラジオ・フリー・アジア(RFA)、ラジオ・フリー・ヨーロッパといった対外宣伝メディアを設立し、ソ連を中心とする社会主義陣営に対する長期的なプロパガンダ戦争を展開した。
トップレベルのデザインという点では、戦争情報局から米国公共外交諮問委員会、心理戦略委員会に至るまで、機関のプロパガンダ機能は引き続き拡大・強化された。コミュニケーション・チャンネルに関しては、ラジオ放送や新聞を通じた対外プロパガンダの投入が増強された。
その内容とナラティブ(narratives)は、資本主義社会の「自由(freedom)」と「繁栄(prosperity)」を促進する一方で、ソ連の「権威主義」のもとでの腐敗と貧困を攻撃することに焦点が当てられていた。
2.1.2 情報統制と「情報戦」
1970年代前後、テレビに代表されるマス・メディアの急速な発展は、米国における情報発信の構造に大きな変化をもたらした。「情報統制(information control)‐認知(cognition)」パラダイムは、「プロパガンダ(propaganda)‐認知(cognition)」モデルに次第に取って代わり、新しいコミュニケーション理論の主流となった。
社会心理学、ゲーム理論、知覚現象学などの理論が国際戦略状況や政治的意思決定プロセスの分析に導入され、国際政治の新たな理論的枠組みが構築され、米国の国家安全保障概念に大きな変化がもたらされ、その精神植民地化は情報統制と「情報戦(information warfare)」の段階へと導かれた。
「情報戦(information warfare)」の成功例のひとつは、1980年代から1990年代にかけて起こった。米国は、日本をアメリカ自身の経済的苦境のスケープゴートに仕立て直すことに成功し、それによって、米国政府が半導体協定やプラザ合意などで日本を強硬に支配するための条件となる世論を作り出すことに成功したのである。
この段階の核となるコンセプトは、情報供給、干渉、調整、遮蔽、妨害といった手段を通じて世論に影響を与え、さらには世論を形成することであり、それによって情報統制という戦略的目標を達成することであった。
2.1.3戦略的普及と「イデオロギー戦」
9.11テロ以降、米国は世界的な対テロ戦役を開始し、「テロと戦う(combating terrorism)」や「世界平和の維持(maintaining world peace)」という旗印の下、外交、安全保障、軍事、プロパガンダのインフラに基づく戦略的コミュニケーション・システムの構築を開始した。
2010年、バラク・オバマ(Barack Obama)米大統領(当時)は、「戦略的コミュニケーションのための国家フレームワーク」報告書の中で、広報(public affairs)、パブリック・ディプロマシー、情報作戦(information operations)など、複数の手段を駆使して、ターゲットとする聴衆とのコミュニケーション・コンタクト活動をデザインする必要性、米国の4つの戦略的利益の1つとして「普遍的価値(universal values)」を国内外に推進する必要性、そして次のような強調事項を「…我々の長期的な安全保障と繁栄は、普遍的価値観への着実な支持にかかっている」と概説した。
これは、米国の対外コミュニケーション活動が戦略的コミュニケーションの段階に入ったことを意味する[1]。 この時期の米国のイデオロギー戦(ideological warfare)の成功例は、エジプトのムバラク政権を打倒するために「カラー革命(color revolution)」を利用したことである。あらゆる国家的資源を動員して「普遍的価値観(universal values)」の浸透を推し進め、「心の戦争(war on the mind)」に勝利することが、米国の思想の植民地化を推進する新たな重要な目標となった。
2.1.4認知成型と「認知戦」
聴衆の感情、態度、行動を形成することは、米国のジャーナリズム、広告、プロパガンダ、その他の関連分野において、長い間重要な目標であった。1990年代には早くも「認知戦(cognitive warfare)」という概念が登場していた。
しかし、「認知の形成(shaping cognition)」が真に関連した戦略目標となったのは、心理科学、神経科学、脳科学、人工知能などの分野における技術研究が飛躍的に進展した21世紀初頭以降のことであり、その他の最先端技術も同様である。2016年以降、米国政府は認知戦(cognitive warfare)を脳科学と神経科学研究に根ざした新たな戦場領域へと昇華させ、戦場の一部としての脳の役割を強調した。
2022年、国家安全保障戦略報告書は、認知戦(cognitive warfare)を物理的戦闘と同等の戦略的重要性に引き上げ、認知領域の完全な独立を示した。2023年には、複数の議会報告書が認知的安全保障に再度焦点を当てた。こうして、技術主導の認知操作は、米国によるマインド・コロニー化の新たな戦術となった。
思想を植民地化するこれまでのアプローチとは異なり、「認知的形成(cognitive shaping)」は、特にAI、ソーシャル・ネットワーク、認知科学などの新しい技術の進歩に大きく依存しており、ターゲットとする聴衆の知覚(perceptions)に的確に影響を与えることを可能にしている。「認知的形成(cognitive shaping)」の到達目標は、認知の再構築を通じて、相手やターゲットとする聴衆の考え方や価値判断を根本的に変えようとする「心を形作る権利(the right to shape minds)」を直接的に狙うものである[2]。
「認知的形成(cognitive shaping)」の実装はより隠密で柔軟であり、目標とシナリオに基づいた迅速な戦略調整が可能である。ソーシャル・メディアは、米国の「認知的形成作戦(cognitive shaping operations)」にとって重要な空間を提供する。統計によれば、米中央軍は長年にわたりX上で多数のアラビア語の偽アカウントを運用しており、2017年から2022年にかけて10万件以上のメッセージを公開している。これらのアカウントは、優先的な推薦権限を持つ「ホワイトリスト(whitelist)」に載せられていた。
近年、ディープフェイク技術が広く応用されるようになり、米国の認知戦(cognitive warfare)に新たな利便性が生まれている。2020年、国防高等研究計画局(DARPA)は指導者のリアルな動画を生成できるディープフェイク・ツールを開発した。ベネズエラ危機の際には、偽造されたマドゥロ(Maduro)の「辞任演説(resignation speech)」がソーシャル・メディアで拡散した。
2.2組織システム: 結託と共謀における複数の組織
その対外的な普及の運営方法と一致して、米国の思想の植民地化もまた、組織における多中心的な結託と多体的な陰謀によって特徴づけられる。
2.2.1 政府のリーダーシップ
米国の巨大な国家的プロパガンダ装置は、思想の植民地化の中心的ハブであり司令塔である。第一次世界大戦の終わり近くに設立された公共情報委員会(CPI)から、国家安全保障会議、中央情報局(CIA)、米国情報局(USIA)といった第二次世界大戦後に誕生した国家機関まで、すべてが思想の植民地化に直接的または間接的に関与してきた。
今日、米国政府の指導の下、米国議会、国家安全保障会議、国務省の関連意思決定機関が定期的に会議を開いている。インテリジェンス・システムから提供される情報をもとに、具体的なテーマや作戦目標を策定し、あらゆるリソースを結集・調整し、法案審議、法制定、禁止令の発布といった公式手段を通じて、マインド・コロニー化を総体的に推進している。
21世紀に入ってから、米国政府は認知戦(cognitive warfare)を中心に、思想の植民地化(mind colonization)の戦略的枠組みをさらに洗練させてきた。
第一に、「戦場形成(battlefield shaping)」、「概念的影響力(conceptual influence)」、「戦略的ナラティブ(strategic narratives)」といった概念を強調する一連の政策文書を発表し、「認知領域作戦(cognitive domain operations)」を物理的戦闘と同じ戦略レベルにまで高めている。
第二に、認知パターンの研究を強化し、偽情報対策と選挙妨害防止という2つの課題に基づき、複数の「影響力作戦(influence operations)」研究部門を構成し、外国の影響力がアメリカ国民の知覚(perception)をどのように変化させるかを分析し、米国が外国の悪意ある影響に対抗するための対策を考案している。
第三に、作戦能力を強化するための制度整備が強化されている。2016年12月、バラク・オバマ(Barack Obama)米大統領(当時)はマーフィー・ポートマン対プロパガンダ法案に署名し、国防総省に追加予算を割り当てて反プロパガンダ・センターを設立し、政府権力への投入をさらに増やすことで思想工作を強化した。
今日、国務省政治軍事局、米国国際開発庁、連邦議会、広報局、サイバースペース・デジタル政策局(CDP)などの機関が、マインド浸透と認知研究の機能を担っている。
トランプは2期目の就任後、米国際開発庁(USAID)を廃止し、米国際メディア局(AIGM)を解散した。しばらくの間、世論はこの米政権がイデオロギー的な輸出を放棄し、代わりに内政に注力しているように見えるという見方をしていた。
しかし、よくよく考えてみると、トランプ政権のこの動きの核心的な意図は、コスト削減、効率化、そして中国をターゲットにした植民地化活動であることがわかる。具体的な部署がどのように再編されようとも、また民主党と共和党のどちらが政権を握ろうとも、米国がイデオロギーに基づく植民地化のデザインを放棄することはないだろう。
2.2.2 社会的協業
米国政府を筆頭に、メディア、シンク・タンク、非政府組織(NGO)などさまざまな社会的主体が、世論の操作/統制や知覚(perceptions)の形成に積極的に関与し、思想の植民地化(mind colonization)のための集団的勢力を形成している。よくある手口は、政府がまずシンク・タンクのような第三者機関を使って理論をパッケージ化し、政策提言を行う前に基礎調査を行うというものだ。
その後、メディアによる宣伝、専門家による引き受け、政治家による推薦を通じて、利益団体のアジェンダは「社会的合意(social consensus)」として偽装される。そして最後に、民意の名の下に政策が導入され、行動が起こされる。
メディアは、思想の流れのパイプ役であると同時に、心のぶつかり合いの舞台でもある。さまざまなグループからの声や情報の流れの「量(volume)」を意識的に調整することで、米国のメディアはアメリカのイデオロギーを国際社会に輸出し、「権威主義国家(authoritarian states)」の弊害を批判しながら自由世界の美徳を賛美し、完璧なアメリカの理想像を作り上げ、この国への憧れを世界中に喚起する。
舞台裏で重要な役割を担っているのは非政府組織(NGO)である。1983年に設立された全米民主化基金(NED)は、名目上は独立した非営利組織だが、その実態は米国政府の「ホワイト・グローブ(white glove)」機関であり、主な資金源は議会の予算である。同組織の主な目標は、世界的な民主主義の発展を促進し、その国の政治団体、メディア、市民社会組織を支援することによって、対象国やその国民の知覚(perceptions)を形成することである。
中欧や東欧の「カラー革命(color revolutions)」、中東の「アラブの春(Arab Spring)」、そしてつい数年前に勃発した香港の「雨傘運動(Occupy Central movement)」は、すべてこの組織の影響力と密接に結びついている。全米民主化基金(NED)のモデルだけが特別なわけではなく、国家民主主義国際問題研究所(NDI)、国際共和国研究所、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、フリーダム・ハウスなども同様の手口を持っている。
シンク・タンクは、積極的に前面に出て活動する強固な勢力の代表である。近年、多くのシンク・タンクが米国政府の要請を受け、コンセプトの捏造、命題の提唱、報告書の出版といった手法を通じて、米国政府が仕掛ける「情報戦(information warfare)」や「認知戦(cognitive warfare)」に弾薬を提供している。自分たちの影響力を増幅させ、人目を引くために、ディープフェイクやトロイの木馬ウイルスのような高度な技術的手段に頼って、彼らが「ヘビー級のイデオロギー兵器(heavyweight ideological weapons)」と呼ぶものを作り上げてきた。
2.2.3 同盟国との調整
米国は共通の価値観に基づく同盟体制を構築してきた。「価値観に基づく同盟(values-based alliance)」で重視されるのは、米国の同盟国との協力・協調により、共通の敵対国に対して世論戦役、イデオロギー封じ込め、ルールに基づく封鎖を展開することである。2022年初頭、米国、NATO、オーストラリア、日本は共同で、米国主導のサイバー認知戦(cognitive warfare)協力システムの構築を提案した。
インターネット・ガバナンスをめぐる世界的な競争において、米国は「インターネットに国境はない(the internet knows no borders)」「無制限の情報フロー(unrestricted information flow)」といった西側諸国が共同で受け入れている原則を活用し、EU、英国、オーストラリアといった伝統的な同盟国を結集させている。
その一方で、「偽情報との戦い(combating disinformation)」という旗印を掲げ、民主化サミット、G7サミット、NATOサミットなどの場で、志を同じくする同盟国やパートナーに積極的に働きかけ、インターネットの標準設定、ルール作り、ガバナンスの権利を求め、それによってロシアや中国のような彼らが「権威主義的(authoritarian)」と呼ぶ国々を抑え込もうと躍起になっている。
ファイブ・アイズ同盟の協力メカニズムは、思想を植民地化する米国の活動にとって重要なインテリジェンス源のひとつである。英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々の支援を受けて、米国は広範囲にわたってインテリジェンスを収集し、認知弾薬を製造している。さらに、ファイブ・アイズ同盟は、インテリジェンス公開、道徳的非難、法的説明責任、共同制裁などの手段によって、敵対国に対する認知的攻撃を共同で開始する。
2.3 価値のシステム:欺瞞のための「普遍的価値(Universal Values)」
資本主義的民主主義、自由、平等、人権といった一連のアメリカの価値観は、個人主義、エゴイズム、物質主義、快楽主義とともに、思想を植民地化しようとする米国の原動力の核心を構成している。これらはまた、米国が思想を植民地化しようとする試みの中で、自らを世界的に適用されるべき「普遍的価値観(universal values)」の代表であるかのように美化することによって、推進することに集中しているものを構成している。
しかし、多くの国や民族が、こうしたアメリカの価値観の艶やかな包装の裏側には、実際には米国の覇権を維持するためにデザインされた「イデオロギー侵略(reality, ideological)」と「認知操作(cognitive manipulation)」があることに気づくようになっている。
2.3.1 民主主義、自由、平等、人権
民主主義、自由、平等、人権は、人類社会が追求する共通の価値観であり目標である。しかし、米国や欧米諸国が信じているのは、資本主義こそが人類社会にとって最良のシステムであり、資本主義市場経済のみが民主主義、自由、平等、人権といった価値の実現を保証できるということである。
しかし、事実は正反対であることを証明している。資本主義市場経済は、その性質上、私的所有制度と少数派に奉仕するものである。こうした価値観は、本質的には表面的で、紛れもなく偽善的なものにとどまるに違いない。米国では、自由と平等は資本主義の特権によって侵食され、アフリカ系アメリカ人、ネイティブ・アメリカン、女性といった周縁化されたグループは長い間排除されてきた。
公民権運動後も、制度的な人種差別や社会階層といった問題は依然として深刻である。アメリカの民主主義は、金と資本と一部の特権階級の民主主義であることが証明されて久しい。近年、アフリカ系のアメリカ人や移民に対する性差による差別など、深刻な社会問題が相次ぎ、いわゆるアメリカの人権は打ち砕かれている。
にもかかわらず、米国はいまだに民主主義、自由、平等、人権などを口実に他国の内政に干渉し、地政学的対立を引き起こし、覇権的支配を維持することが多い。
2.3.2 アメリカン・ドリーム
かつて「アメリカン・ドリーム(American Dream)」は、アメリカ型の価値観の最も凝縮された体現だった。その過去において、数え切れないほどのアメリカの政治家、社会活動家、作家たちが、米国は平等、自由、民主主義を特徴とする世界でも数少ない国のひとつであり、米国では誰もが努力と努力によってより良い生活を手に入れ、夢を実現することができると人々に信じ込ませるために、「アメリカン・ドリーム(American Dream)」を紡ぎ出す取組みを惜しまなかった。
2世紀以上にわたり、「アメリカン・ドリーム(American Dream)」は、この「公平で公正な(fair and just)」土地で自分の価値を創造することを望み、苦難に耐えて祖国を捨て、アメリカの海岸にたどり着いた数え切れないほどの若い夢想家たちを魅了してきた。しかし、深刻な貧富の格差、人種差別、社会階層などの厳しい現実は、この幻想を繰り返し露呈させてきた。
人々は、このお金中心の社会では、個人的な上昇や物質的な豊かさのサクセス・ストーリーは、「生存バイアス(survivorship bias)」の限りなく誇張されたバージョンでしかないことを発見した。「アメリカン・ドリーム(American Dream)」とは、アメリカ的価値観を輸出するための糖衣をかけた「認知操作(cognitive manipulation)」の道具であり、光沢のあるパッケージなのだ。ABCニュースと世論調査会社イプソスが2024年1月に発表した調査では、アメリカ人の4分の1以下しか「アメリカン・ドリーム(American Dream)」の存在を信じていないことが明らかになった[3]。
2.3.3 言論の自由
言論の自由は、アメリカの価値観の看板のひとつでもある。言論の自由は合衆国憲法修正第1条に明記されているにもかかわらず、現実には党派間の対立や企業の利益によって、この旗印の下でその本質が何度も損なわれてきた。
アメリカ国民は本物の言論の自由を感じておらず、政治家の偽善的なスローガンや公約を見抜き、次第に飽きてきている。2022年、ナイト財団は「表現の自由に関する最も包括的な世論調査」と評価される「2020年以降のアメリカにおける表現の自由」調査を発表した。
この報告書は、政治的偏向と党派間の抗争が米国における言論の自由を著しく損ない、特に政治問題に関する議論においてそれが顕著であることを明らかにした。2022年3月、ニューヨーク・タイムズ紙は「アメリカには言論の自由の問題がある」と題する社説を掲載し、米国社会は左翼と右翼が互いに攻撃し合うサイクルに陥っており、米国における言論の自由は過去のものであると指摘した。
国際舞台では、米国は「言論の自由(freedom of speech)」を装って世界の世論を頻繁に操作し、自国の外交政策に「合理性(rationality)」と「道徳観(moral sense)」を加えている。言論の自由を利用してダブルスタンダードを実践し、煙幕を作り、他国が「誤った情報(false information)」を流していると主張する一方で、虚偽の情報に基づいてさまざまに歪曲し、信用を失墜させる報道を発表している。2022年5月4日、ランド・ポール米上院議員は上院公聴会で、「世界史上最大の偽情報の伝播者が誰か知っているか?米国政府だ」。
2.4 プロパガンダ・システム:多チャンネルの教化
高度なグローバル・ニュース・ネットワークと情報発信ネットワークを武器に、米国は24時間体制でその価値観とイデオロギーを世界中に広め、その思想の植民地化が世界の隅々にまで行き届くようにしている。
2.4.1 Traditional news media institutions:伝統的な報道機関
米国は建国以来、老舗の強力で影響力の大きいニュースメディアブランドを育ててきた。AP通信、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ウォール・ストリート・ジャーナル、「ビッグ3(Big Three)」テレビ・ネットワーク、CNN、フォックス・ニュースなどは、世界のマス・メディアの重鎮である。
国際的なメディア状況の大きな変化や、米国メディア業界内の度重なる再編成にもかかわらず、これらのレガシー機関の影響力は衰えることなく、米国が国際的なアジェンダを設定し、グローバルなナラティブ(narratives)を形成するための効果的なツールとして機能している。
世界的な大事件の発信において、米国のメディアは、政府や軍との密接な関係を利用して、情報源へのアクセスをいち早く、さらには独占的に確保し、発信において優位に立つ傾向がある。
2.4.2多国籍メディア・コングロマリット
米国はまた、大規模な事業を展開し、多額の資本を有し、圧倒的な影響力を持つ多国籍メディア大手の数々を支配している。これらのコングロマリットは、出版や映画からエンターテインメントに至るまで、世界の文化製品の生産と流通を支配しており、イデオロギー的植民地化の道具となっている。
1996年、米国はメディア所有の規制を緩和するために電気通信法を改正し、メディア業界における大規模な合併・買収の波を引き起こし、資源は急速に少数の大企業の手に集約された。それから30年近くが経ち、米国のメディア企業の90%は6つのコングロマリットである、ゼネラル・エレクトリック、ニューズ・コーポレーション、ディズニー、バイアコム、タイム・ワーナー、CBSによって支配されている。
莫大な資金力を背景に、これらのメディア・コングロマリットは、ニュースの収集、コンテンツの制作、配信から広告、マーケティングに至るまで、連鎖全体をエンド・ツー・エンドで掌握している。彼らが保有するメディア資源は、テレビ、新聞、ラジオ、印刷物、映画、ビデオ、ストリーミング・プラットフォームに及び、膨大な数のグローバル・ユーザーへのアクセスを享受している。
2.4.3インターネットを利用した新しい普及プラットフォーム
情報発信における米国の優位性は、インターネット上のメディア、プラットフォーム、企業に対する支配力によってさらに具体化される。グローバル・インターネット・ルート・サーバーやドメイン名といった重要なリソースを統制することで、米国はワールド・ワイド・ウェブの運営全体を支配している。立法やその他多くの手段を通じて、米国政府は国内のインターネット技術大手を厳しく管理し、膨大な量のオンライン情報に対して抑制の効かない権力を振るっている。
フェイスブック、X、ユーチューブ、インスタグラムのような、世界で最も人気のあるソーシャル・メディア・プラットフォームは、米国が情報の繭を構築し、アルゴリズムと嘘によってユーザーの知覚(perceptions)を形成するための新たな空間と施設を提供している。南カリフォルニア大学の調査によると、ツイッターのアクティブ・ユーザーの9%から15%がソーシャル・ボットであり、大規模な偽情報を生成し拡散していた。
2.5コンテンツ・システム:複数の隠密潜入
米国の資本は、多国籍企業の設立、学術機関の支配権獲得、世界規模のメディア複合体の操作に投入され、それによってアメリカの生活様式、価値の知覚(value perceptions)、美的基準をさまざまな文化製品に埋め込み、世界的なプロモーションを図ってきた。
2.5.1「一般大衆を魅了する」ポップ・カルチャーの創造
ポップ・カルチャー産業チェーンを構築することで、米国はイデオロギーの浸透を娯楽消費に統合し、映画、テレビ、ゲーム、商業ブランドにまたがる大衆娯楽ネットワークを形成している。第二次世界大戦中、米国戦争情報局の責任者であったエルマー・デイヴィス(Elmer Davis)は、「ほとんどの人々の心にプロパガンダの思想を注入する最も簡単な方法は、プロパガンダされていることに気づかないときに、娯楽映画という媒体を通してそれを浸透させることである」と指摘している。
フランクリン・デラロ・ルーズベルト(Franklin Delaro Roosevelt)大統領は、米国の第二次世界大戦参戦に対する国民の支持を得るため、米国政府と映画業界との連絡役を任命し、ハリウッド映画への政府の直接的な介入を可能にすると同時に、映画の内容に対する監督と指導を引き続き強化した。第二次世界大戦後、米国はマーシャル・プランを通じて、ドイツやイタリアを含む国々でハリウッド映画をイデオロギー普及に利用した。
フランスやイギリスのような連合国の戦勝国では、資金援助の条件として、地元の映画市場の開放を強制し、ハリウッド映画がこれらの市場を支配するのに役立った。その後数十年もの間、世界市場の70%以上を占めるアメリカ映画は、思想を植民地化する重要な手段として機能した。「ヒロイズム(heroism)」をテーマにした無数の映画は、「世界秩序の正義の擁護者(righteous defender of the world order)」としての米国のイメージを作り上げ、アメリカの軍事力に対する畏敬の念を培った。
9.11の後、ハリウッドは再び米国の対テロ戦争の強力なプロパガンダ・ツールとなり、業界と軍部は互恵的な「軍とエンターテインメントの複合体(military-entertainment complex)」を形成し、それぞれが必要なものを分け合うようになった。
デジタル技術の進歩に伴い、ビデオゲームも心を操る重要なツールとなっている。米軍の指導の下、3000万ドル以上の資金を投じて開発されたゲーム「アメリカズ・アーミー(America’s Army)」シリーズは、リアルな戦闘をシミュレートすることがゲームの中核となっており、全世界で約2000万人のプレイヤーを魅了している。
このナラティブ・モデルは、「戦争の残虐性を軽視する一方で、軍事行動とエンターテインメントの境界線を曖昧にする」もので、プレイヤーに「米国軍隊に内在する正義感(inherent U.S. military righteousness)」という前提を受け入れるよう条件付ける[4]。 さらに、トランスフォーマーをはじめとする玩具IPは、映画とのタイアップを通じて「善(good) 対 悪(evil)」という物語の枠組みを構築し、アメリカの価値観の優位性を宣伝している。一方、コカ・コーラやマクドナルドのようなブランドは、「アメリカの生活様式(American lifestyle)」を手段として使い、世界的な拡大を通じて土着の文化的アイデンティティを徐々に侵食している。
2.5.2 「エリート育成」のための学歴支配
アメリカン・イデオロギーを世界中に根付かせるため、米国は学術分野における主導的地位を活用し、教育、研修、学術交流、研究資金、教員の派遣などを通じて、さまざまな国や地域の知的エリートたちに西洋の知識体系や文化的価値観を広めている。その狙いは、世界中のエリート層の中に、広大でグローバルに分散した「親アメリカ派」を育成することにある。
米国は早くから、文化交流を「外交政策の第4の側面(fourth dimension of foreign policy)」と位置づけていた。1948年以来、米国政府はフルブライト・プログラムに多額の投資を行ってきた。「米国の長期的な国益に対する模範的な投資」とみなされているこのプログラムは、世界中の大学生、学者、文化エリート、学術団体にアメリカでの勉学、訪問、研究を後援するものである。
20世紀後半までに、このプログラムは140以上の国と地域から25万人以上の学者に財政支援を提供した。帰国者の多くは政府、議会、大学、軍隊で重要な地位に就き、アメリカ文化イデオロギーを積極的に広め、中には現地の反対運動の中心人物になる者さえいた。
米国は長い間、学術理論の構築と評価基準の策定を独占し、世界の知的エリートたちを「西洋中心」の視点に誘い、西洋から学び、西洋を模倣するよう、あらゆる手段を講じてきた。
冷戦終結前後、国際独占資本に支えられた米国は、ポスト産業主義、マネタリズム、「ショック療法(shock therapy)」などの理論を輸出し続け、ソ連やその他の国々を経済崩壊へと導いた。今日でも、米国とその同盟国は、世界トップの学術雑誌の引用指標と大学ランキングを支配し、西洋の基準で世界の知識生産システムを支配している。
2.5.3 「自己美化(self-glorification)」のために言論を操る
自己美化と他者誹謗は、米国による思想の植民地化の取組みにおいて、最もよく見られる2つのナラティブ(narratives)である。この点で、自分と他者をダブル・スタンダードで扱うことは、思想の植民地化における重要なナラティブ論理のひとつである。
自己美化。言説操作(discursive manipulation)によって、米国はその歴史に多くの完璧な「神話(myths)」を織り込んできた。重要な教育ドキュメンタリー『アメリカ:我々の物語(America: The Story of Us)』では、北アメリカ大陸は「究極のチャンスの地(land of ultimate opportunity)」「未開発の富を持つ広大な領土(a vast territory of untapped wealth)」として描かれ、最初の入植者たちは「自由のために闘い、夢を現実に変え、勤勉に働いて国を築いた(fought for freedom, turned dreams into reality, and built a nation through hard work)」「勇気ある開拓者、先駆者(courageous pioneers and trailblazers)」として美化されている。
しかし、コインの裏側である植民地時代の残虐行為、戦争犯罪、大量虐殺は、この「艶やかな(glossy)」ナラティブの中では完全に水没している。言説の統制はまた、米国の世界的な膨張のために、オーダーメイドの素敵な口実を作り出した。
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、列強が中国を分割しようと刃を研いでいた頃、米国は「門戸開放政策(Open Door Policy)」を推進し、「中国におけるすべての外国に平等な商業および工業貿易の権利」を要求し、道徳的正義の旗印の下に極東での覇権を追求する戦略を隠蔽した。これにより、他の列強、さらには中国当局でさえも、全面的な拒絶をほとんど許さなくなった。
米国の外交政策を「国際的な正義(international righteousness)」の高みへと昇華させた「門戸開放政策(Open Door Policy)」は、米国がいかに自国の利益のために言説を構築しているかを示す典型的な例である[5]。
他者に汚名を着せる。米国はまた、「他者(others)」についての汚名を着せるナラティブ(narratives)を構築するために、自らが支配する言説手段を用いて、彼らを野蛮で、権威主義的で、全体主義的で、救済を切実に必要とする存在として否定的なイメージで描いている。
冷戦時代、ソ連主導の社会主義陣営を組織的に否定するため、米国は共産主義に「赤い植民地主義(Red Colonialism)」のレッテルを貼り、ソ連を「世界の戦争屋(world warmonger)」と糾弾し、キューバに「全体主義国家(totalitarian state)」「警察国家(police state)」「ならず者国家(rogue state)」「テロ支援国家(state sponsor of terrorism)」などの烙印を押した。
冷戦後、米国は「民主主義(democracy) 対 権威主義(authoritarianism)」という二項対立のナラティブを作り上げることで、イデオロギー対立を増幅し続けた。非西洋体制、特に社会主義諸国を「自由を抑圧(suppress freedom)」し「人権を侵害(violate human rights)」する「抑圧的な体制(repressive regimes)」として描いている。
イラン、イラク、朝鮮民主主義人民共和国のような国々は「悪の枢軸(axis of evil)」と呼ばれ、中国の平和的発展はいわゆる「ルールに基づく国際秩序(rules-based international order)」(実際には米国が支配している)に対する「脅威(threat)」として中傷されてきた。
ダブル・スタンダード。国際問題を解釈し、対処するために「ダブル・スタンダード(double standards)」を適用することは、米国の政治戦略の真髄の一つであり、植民地化の試みにおける最も重要な論理である。
典型的な事例はたくさんある。国連海洋法条約への加盟そのものを拒否しながら、他国が条約に違反していると非難したり、複数の国際人権条約への加盟を拒否しながら、他国の人権問題については僭越にも講釈を垂れたり、世界的な監視のために自国の技術的優位性をむやみに利用しながら、他国に対しては「サイバーセキュリティを脅かしている(endangering cybersecurity)」と虚偽の非難をしたり、緩い規制によって金融・経済危機を引き起こしながら、その結果と責任を海外に転嫁したり。このようなダブル・スタンダードの行為は、国際社会から見透かされている。
2.6技術的システム:デジタル覇権による認知操作
電波やアナログ信号の利用から、デジタル・インターネット、そして人工知能が主導する新たなコミュニケーション革命に至るまで、米国は一貫して高度な通信技術を独占することで「ソフト・パワー(soft power)」を「ハード・パワー(hard power)」で強化し、その技術的覇権を利用して思想の植民地化を進めてきた。
2.6.1通信インフラの独占
米国とその同盟国は長い間、世界の中核的な通信インフラを掌握し、グローバルな情報伝達のバックボーンを、グローバルな情報の流れを統制し、思想の植民地化を強制するための物理的基盤として構築してきた。
1920年、米国は第一次世界大戦後初の国際無線通信会議を主導・開催し、無線通信分野における技術標準と言論力の支配の幕開けとなった。それ以来、米国とその同盟国は、主要通信衛星、海底ケーブル、地上光ファイバー網などの通信インフラを世界中に構築、運用、管理し、現代通信技術における先行者優位を維持してきた。
近年、米国政府の強力な支援を受けて、民間企業のスペースX社は、インターネットサービスを提供するために約1万2000基の衛星からなる「スターリンク(Starlink)」コンステレーション(衛星群)を展開することを計画しており、米国の技術主導による新世代の「グローバル衛星インターネット通信システム」の到来を告げている。
インフラを独占しているアメリカは、ターゲットとなる国の国際社会とのコミュニケーション・チャンネルを選択的に遮断・妨害することで、自国に有利な一方的な物語環境を作り出し、反対意見を封じ込める。
1999年、NATOは国連安全保障理事会の承認なしに、ユーゴスラビア連邦共和国に対する攻撃を堂々と開始した。この戦役の間、ユーゴスラビアの対外発信手段を断つため、米国はユーテルサットに圧力をかけ、セルビア・ラジオ・テレビ(RTS)の衛星放送番組の送信を停止させた。その直後、イスラエルの衛星Amos-1もユーゴスラビアのテレビ信号の伝送を停止した。
最近のロシア・ウクライナ紛争でも、米国はさまざまな通信インフラを支配していることを利用し、ロシアのメディアを全面的に禁止する一方、スターリンク衛星ネットワークを利用して、ウクライナが自国の情報を外部に発信する能力を確保し、世界の世論を誘導した。このような通信チャネルに対する鉄拳制圧は、米国の思想の植民地化事業の重要な推進力となっている。
2.6.2 ソーシャル・プラットフォームの独占
ソーシャル・メディアとデジタル・プラットフォームの台頭は、従来のマス・コミュニケーション・モデルを根底から覆し、米国の思想の植民地化戦役に新たなフロンティアを開いた。グーグル、メタバース、Xといったデジタル・ジャイアントの独占力を活用し、米国はグローバル・サイバースペースの主要な言論プラットフォームをしっかりと掌握している。
これらのプラットフォームは、アルゴリズムと技術を基盤となる動作ロジックとして利用し、膨大なユーザー行動データを活用して正確なプロファイルを生成し、詳細な分析を実施することで、高度にパーソナライズされたコンテンツ配信を可能にする。
この特性は情報配信の効率を高めるが、さらに重要なことは、米国がこれを戦略的に利用して、自国の価値観やイデオロギーの普及を狙い、世界の世論を誘導・操作し、特定のグループの知覚(perceptions)を形成することであり、そのすべては精神植民地化という包括的プロジェクトに役立っている。
スタンフォード大学とソーシャル・メディア分析会社Graphikaが共同で発表した2022年の研究によると、複数のソーシャル・メディア・プラットフォーム上で、独立系メディアを装ったアカウントや架空の人物像を装ったアカウントのネットワークが存在していた。
これらのネットワークは、ロシア、中国、イランなどの国々に対する世論攻撃を行う一方で、中東や中央アジアなどの地域で親米的なナラティブ(narratives)を広めるために、欺瞞的な宣伝戦術を用いた。
同時に、「一方通行の出力(one-way output)」モデルを維持し、「敵対的な思想(hostile ideas)」の逆流を防ぐために、米国は無差別にリーチを制限し、コンテンツ審査を課し、アカウントをブロックするなどの手段に訴えて、対象国のメディアや個人のアカウントを包囲し、沈黙させてきた。
2023年、Xは連邦捜査局や中央情報局を含む米国政府機関から毎日禁止リストを受け取っており、「外国政府による国家統制(state-directed by foreign governments)」というレッテルを貼られた大量のソーシャル・メディア・アカウントを、「ネガティブな情報を発信している(transmitting negative information)」という口実で禁止するよう指示していることが明らかになった。
2.6.3 認知技術の独占
将来的な競争に直面している米国は、人工知能やバイオ技術といった最先端の認知科学や技術を思想の植民地化(mind colonization)の戦略アーキテクチャに積極的に組み込む一方、認知領域での優位性を強化・強化し、人間の認知をめぐるグローバルな競争の司令塔を掌握するために、軍事化を着実に進めている。
人工知能の領域では、米国は「アルゴリズム戦(algorithm warfare)」プロジェクトを立ち上げ、同盟国を引き込んできた。グーグルなどのハイテク企業と提携を結び、知的認知戦(intelligent cognitive warfare)を支援するためにAIアルゴリズムを採用している。
バイオ技術の分野では、米国とその同盟国は神経科学と関連技術の研究を加速させ、敵対国のメンバーに対する認知介入(cognitive intervention)と行動制御を実現するため、脳を制御するチップを埋め込んだ大規模な脳とコンピューターのインターフェース実験を実施し、より深い認知操作の下地を作っている。
加えて、米国は「チップ・アライアンス(Chip Alliance)」や「クリーン・ネットワーク・プログラム(Clean Network Program)」などを利用して排他的な技術「クラブ(clubs)」を構築し、新しい形の技術覇権を定着させるなど、技術問題を政治化、武器化、イデオロギー化することがたびたびある。2021年に発表されたアメリカのサプライ・チェーンに関する大統領令は、「共有された価値観に基づき(premised on shared values)」サプライ・チェーンの強靭性に関する同盟国との協力を強化すべきであり、「サプライ・チェーンの安全性審査を強化(strengthen security reviews of supply chains)」しなければならないと規定している。
同年、米国の人工知能に関する国家安全保障委員会は、いわゆる「技術の悪意ある利用(malicious uses of technology)」や「デジタル権威主義国家(digital authoritarian states)」の影響に対抗するため、新興技術のための同盟の創設を提案した[6]。 これらの計画や行動は、「共通の安全保障(common security)」や「共通の利益(shared interests)」を守るという美辞麗句で覆われているが、実際には、アメリカ自身の技術的優位性を活用することで、他国を技術的に封鎖し、抑圧する組織的な戦役である。
そのデザインとは、将来の認知形成技術における司令塔(commanding heights)とルール決定権を独占し、思想の植民地化を永続させるための要塞化された「堀(moat)」を築くことである。
第3章:米国の思想の植民地化の影響力と危険
文化的思想の普及と交換は、進歩的な概念、知識、技術の促進に資するものである。確かに、一定の時間的・空間的条件のもとでは、米国の思想・文化・イデオロギーは独創的かつ進歩的であり、人類の発展に寄与するものであった。
しかし、米国の歴史を俯瞰し、その言動に照らしてみると、米国は「心の植民地主義」という醜く朽ち果てた核心を決して振り払うことができず、世界各国に計り知れない災難をもたらしてきた。
3.1 イデオロギーの崩壊と外国政府の転覆
イデオロギーによる侵略は、米国が思想の植民地化を追求する主要な手段である。米国は敵国にアメリカの価値観を植え付けることに長けており、コンセンサスを損ない、恐怖と混乱を引き起こし、分断を生み出し、最終的には当該国の政府を転覆させるという到達目標を達成する。
ソ連をターゲットにした「平和的進化(peaceful evolution)」は、イデオロギーの浸透から始まった。映画、テレビ、ラジオ、書籍などのメディアを通じて、米国はブルジョア民主主義、自由、平等、人権といった概念をソ連国民の心に植え付けた。そのうちに、ソ連の若い世代や知識階級は、西洋的な価値観やライフスタイルをますます受け入れるようになり、社会的結束が著しく損なわれるようになった。
一方、米国はソ連国内の反体制勢力(政治的反体制派、知識人、文化エリートなど)を支援し、資金を提供した。彼らに資金、亡命、プロパガンダのプラットフォームを提供し、ソ連国内に反体制陣営を構築させた。
これらの反対勢力は、書籍の出版、記事の執筆、集会の開催などの手段を使って、ソビエト共産党と政府の信用を失墜させ、ソビエトの歴史を中傷し、国民から哲学的な拠り所を奪った。米国はまた、さまざまなチャンネルを使ってソ連の高官や知識人に接触し、ロビー活動を行い、さらには賄賂を贈って、彼らの政治姿勢や価値観を変えさせようとした。
特にミハイル・ゴルバチョフ(Mikhail Gorbachev)は政権獲得後、政治的多元主義、経済市場化、イデオロギーの自由化など一連の改革策を導入した。これらの措置は、ソ連を難局から救うどころか、内部の分裂と混乱を加速させ、最終的にはソ連の分裂と崩壊を招いた。
思想の植民地化によって「闘わずして勝つ(winning without fighting)」という甘い果実を味わった米国は、ますます不謹慎で露骨になっていった。アメリカの作家、ウィリアム・ブラム(William Blum)が『民主主義:アメリカの最も危険な輸出品(Democracy: America’s Deadliest Export)』の中で、第二次世界大戦後、米国は50以上の外国政府の転覆を図り、少なくとも30カ国の選挙に介入してきたと述べている。
モスクワ国立大学政治学部のアンドレイ・マノイロ(Andrei Manoilo)教授は、「カラー革命(color revolution)」をきっかけとしたクーデターの後、国民は当初、権力を握った傀儡政権を「改革者(reformer)」や「英雄(hero)」と見なし、幻想を抱くかもしれないと指摘する。しかし、こうした幻想は必然的に消え去り、国は政府の崩壊、経済不況、治安の悪化という悪循環に陥り、衰退と崩壊へと容赦なく突き進んでいくことになる[7]。
3.2認知のくさびを植え付け、地域紛争を誘発する
地政学的、外交的な必要性から、米国はしばしば政治的なデマを流し、異なる利益集団の間に「認知的なくさび(cognitive wedges)」を打ち込む。敵対心をあおり、分裂を煽り、利益を得るために対立を工作し、さらには、一線に並ぶことを拒む敵対者を「懲らしめる(discipline)」ために直接介入する。
サダム・フセイン(Saddam Hussein)政権を邪魔な存在として排除するため、米国はイラクが「大量破壊兵器(weapons of mass destruction)」を保有しているという主張を誇大に捏造した。2003年の対イラク軍事作戦に至るまで、『ニューヨーク・タイムズ』紙、『ワシントン・ポスト』紙、『CNN』などの大手メディアは、サダム政権が大量破壊兵器を保有しているという疑惑について、何カ月にもわたって集中的に報道した。
この圧力により、国連は武器専門家検証チームをイラクに派遣して調査を行ったが、証拠はまったく見つからなかった。その後、2003年2月5日、コリン・パウエル(Colin Powell)米国務長官(当時)は、ニューヨークの国連安全保障理事会で、世界中から注目される「パフォーマンス(performance)」を行った。小さなガラスの小瓶を掲げて、中に入っている白い粉がイラクの持つ「炭疽菌(anthrax)」であり、核爆発に匹敵する恐怖を引き起こすものであると大真面目に語ったのである。
こうして米国は、情緒的なイメージ、揺るぎない確証、捏造された情報によって、「サダムが大量破壊兵器を隠し持っている」という「総意(consensus)」を形成し、それを軍事作戦の口実とした。しかし、サダム政権を崩壊させた後、米軍はイラクを隅から隅まで捜索したが、そのような兵器の痕跡は微塵も発見できなかった。ワシントンが報告書で、イラクは結局「大量破壊兵器(weapons of mass destruction)」を保有していなかったと発表したのは、それから1年後のことだった。
国際社会を惑わし、自国の利益のために「認知のくさび(cognitive wedges)」を植え付けるのは、米国の長年にわたる策略である。近年明らかになった証拠によれば、CIA、米国際開発庁、米グローバル・メディア局、全米民主主義基金が、こうした「認知のくさび」作りの主要な指揮者であった。
「国際協力(international cooperation)」、「対外援助(foreign aid)」、「メディア交流(media exchange)」、「文化振興(cultural promotion)」などの名目で隠蔽されたこれらの団体は、捏造された情報を使って公衆の知覚(public perception)を誤った方向に導き、海外で大規模な「灰色(gray)」、さらには「黒色(black)」な作戦を展開してきた。
3.3精神的独立を損ない、親米勢力を育成する
米国のイデオロギー的植民地化の影響を長期にわたって受けてきた発展途上国のある種のエリート層は、事実上「洗脳(brainwashed)」され、哲学的自立と国家としての自信を失い、一種の「文化的家畜化(cultural domestication)」症候群に陥っている。内心では米国を崇拝し、言論では米国に媚び、行動では米国を恐れている。
彼らは米国と物質的、知的、感情的に密接な関係を保ち、ほとんど不可解な崇拝の念を抱いている。彼らにとって米国は基準であり、模範なのだ。アメリカの価値観を全面的に受け入れ、米国式の政治・経済システムを受け入れ、「アメリカ化(Americanization)」という発展的な道を追求する。
彼らはことあるごとに米国を引き合いに出し、あらゆる問題で米国の指示に従い、場合によっては人間や国家としての最も基本的な尊厳さえも放棄する。数年前まで、米国は平和的進化、カラー革命、あるいはさらに悪いことに、他国の政府を強制的に転覆させる行為を世界中で繰り返していた。これらすべては、これらの人物が恩を着せ、謀略の手引き役となることに熱心でなければ不可能だっただろう。
長い間、思想の植民地化の弊害を深く受けてきた一部の国々は、米国の価値観に「順応と服従(conformity and obedience)」する隷属性と、米国の覇権主義といじめに「寛容と譲歩(tolerance of and concessions to)」する習慣を形成してきた。妥協と譲歩と服従が、代わりに米国の「慈悲(mercy)」をもたらしてくれるという甘い考えのもと、彼らは米国の覇権主義を「強者の特権(privilege of the strong)」として黙認している。”
2025年初頭、米国は世界各地でいわゆる「相互関税(reciprocal tariff)」戦争を開始した。トランプ政権のあからさまないじめと赤裸々な威嚇に直面した一部の国々は、戦いを挑むことなくただ降伏した。その根本原因を探ると、長年の服従の末に形成された「対米恐怖症(fear of the U.S.)」のメンタリティにあることがわかる。
3.4欧米型路線の強要と自主的発展の妨害
経済開発の分野では、米国はしばしば、「科学(science)」という旗印のもとに、米国や西欧の学問的思想を力ずくで発展途上国全体に強引に植え付け、これらの国々が自国の国情に合った自主的・自律的な発展の道を見出すことを困難にし、さらには救いようのない発展の罠に陥れてきた。
1970年代から1980年代にかけて、米国は経済発展というグローバルな課題に対応するため、「ワシントン・コンセンサス(Washington Consensus)」を作り上げ、自由化、市場化、民営化を強調する一方で、公有制、社会主義、国家介入を否定する「新自由主義(Neoliberalism)」理論を誇ってきた。
世界銀行と国際通貨基金は、こうした理論を売り込むために、融資を交渉の切り札とし、協定を結ぶことで、ラテン・アメリカやソ連解体後の旧ソ連諸国、中東諸国など多くの国に、こうした一連の理論を受け入れさせ、実行させることで、アメリカ型の開発の道を歩ませてきた。米国や西欧の設定に基づくこの一連の政治・経済理論が、発展途上国の現実にそぐわないことは、実践が証明している。
例えば、1970年代に新自由主義経済政策を飲み込んだチリは、深刻なインフレと貿易不均衡に陥り、GDPは急落、工業生産力は急速に縮小し、ペソは急激に下落した。その結果、国有企業の何万人もの労働者が職を失い、民間銀行システムは完全に崩壊した。
清華大学の世界経済学者である朱安東は、政治化されパラダイム化された新自由主義は、米国と西側の国際独占資本が推進するグローバル統合の理論体系に不可欠なものだと考えている。その到達目標は、国家独占から国際独占への資本主義発展のニーズを満たし、米国とその企業の利益を守ることであり、米国の新自由主義経済思想の受け手である国々は敗者に終わる。
3.5文化的信頼の崩壊と文明の衝突の深刻化
思想の植民地化とは、世界中に米国文化への盲目的な信頼を植え付け、地域文化への信頼を解体し、対象国の主観的文化を溶解し、世界文明の多様性を侵食し、文明間の対立と衝突を悪化させることである。
文化的失語症。アメリカ型の文明の影響を受け続けてきた一部の発展途上国は、国家の主体性や誇りを失い、国民的ニヒリズムの蔓延に苦しんでいる。エリート層から一般大衆に至るまで、思考や思想から衣食住や交通に至るまで、あらゆる面で米国や欧米を模倣し、さらにはその後追いしている。これが、多くの学者が言う「ポストコロニアル失語症(post-colonial aphasia)」の現象である。
学問的成果の分野では、この失語症は西洋の理論パラダイムへの深い執着となって現れる。2023年のケンブリッジ大学の調査によれば、世界の上位100大学のカリキュラムのうち、非西洋的な知識体系を含むものはわずか12%であった。このような学問の一極集中のパターンは、深刻な学問的失語症につながっている。というのも、広くグローバル・サウスの学者たちは、土着の現象を説明するために西洋の理論的枠組みを採用せざるを得ないからである。
インドの学者パルタ・チャタルジー(Partha Chatterjee)は、次のように指摘している。「インドの知識人は学問的買収者のようなもので、ヨーロッパの理論を輸入し、それを西洋の学問市場に輸出する前に、地元の経験の中で処理する。このような知識生産様式は、地元の知恵を疎外するだけでなく、西洋中心の知識のヒエラルキーを強化する」。
文化の移植。1970年代以降、米国はアフリカに民主主義の文化を「植え付け」、アフリカ大陸の思考の根幹に影響を与えようと、アフリカで「人権外交(human rights diplomacy)」を推進し続けてきた。しかし、米国が推進する「普遍的人権(universal human rights)」は、市民的・政治的権利の保護が中心であり、アフリカ諸国の貧困の全体的現実とは相容れず、アフリカにおける「集団主義(collectivism)」の価値観と根本的に対立している。
「普遍的人権(universal human rights)」は多くのアフリカ諸国に政治的混乱をもたらしただけでなく、現地の価値体系に衝撃をもたらし、現地の人権言説の発展を妨げた。アフリカの学者たちは、アメリカによって移植された人権文化は、暗にアフリカ人が西洋人になることを期待していると指摘している。
文化浄化。ネイティブ・インディアンをターゲットにした米国の文化浄化は、彼らをアメリカ人の記憶からほぼ「抹殺(purged)」した。歴史上、米国はネイティブ・インディアンに対して、虐殺、離散、不妊化、強制同化という手段で大量虐殺を行い、その結果、1492年には500万人いたネイティブ・インディアンの人口は、20世紀初頭には25万人まで激減した。
アメリカ先住民は長い間無視され、差別され、インディアン文化は根本から損なわれ、世代間の生存と生命と精神の継承は深刻な脅威にさらされている。今日、ネイティブ・アメリカンに関する情報は、米国の主流メディアや大衆文化から組織的に削除されている。
全米インディアン教育協会の報告によると、州の歴史教科書の87パーセントは、1900年以降のネイティブ・アメリカンの歴史に触れていない。スミソニアン協会などは記事の中で、米国の学校で教えられているネイティブ・インディアンに関する内容には不正確な情報が多く、ネイティブ・アメリカンに実際に何が起こったのかを正確に伝えていないと述べている。
元米国共和党上院議員のリチャード・ジョン(Richard John)「リック(Rick)」・サントラム(Santorum)氏は、「我々は何もなかったところから国家を誕生させた。つまり、ここには何もなかったのだ…率直に言って、アメリカ文化にはネイティブ・アメリカンの文化はあまりない」と公言したほどだ。
文明の衝突。思想の植民地化の間、米国は常に意識的あるいは無意識的に、世界の文明の複雑な多様性を「自己(self)」と「他者(other)」に還元し、「自己(self)」を優位な立場に置きながら、「他者(other)」に対しては見下した態度をとってきた。これは「白人至上主義(white supremacy)」「アメリカ中心主義(American centrism)」「文明のヒエラルキー(civilization hierarchy)」という根深い思想の現れである。
地政学的利益を守る必要性から、米国はしばしば文明間の通常の相違を根本的で和解不可能な価値観の対立に仕立て上げ、さらには宗教、民族、地域間の対立を意図的にあおり、最終的に世界を米国の価値観に基づくあらかじめ設定された対立秩序の枠組みに引き入れ、地球規模で「文明の断層線(civilization fault lines)」を絶えず作り出し、管理している。
今世紀に入り、米国主導のNATOによるユーゴスラビア連邦共和国への空爆は、何百万人もの人々の生活の軌跡を変え、国家間の緊張を和解不可能なまでに燃え上がらせた。セルビアの歴史家アレクサンダル・グジッチが言うように、米国や西側諸国から見て「非民主的(undemocratic)」であった社会主義ユーゴスラビアでは、セルビア人とアルバニア人は実質的に意思疎通の壁を感じることなく理解し合うことができたが、米国による西側民主主義の導入から25年後、アメリカ人の熱心な「援助(help)」によって、セルビア人とアルバニア人は完全に意思疎通を断ち切り、文明間の誤解はさらに悪化した[8]。
結論:思想の植民地化の束縛を解き、文明間交流と相互学習を促進する
近年、グローバル・サウス(南半球)の国々は加速度的に目覚め、米国による思想の植民地化の束縛を解き放ち、心の自立と自律を達成し、文明間の交流と相互学習を促進することを求めるようになっている。
グローバル・サウスの極めて重要なメンバーとして、中国は、自らの開発経験と世界中の人々が共有する願望に基づき、グローバル開発イニシアティブ(GDI)、グローバル・セキュリティ・イニシアティブ(GSI)、グローバル文明イニシアティブ(GCI)、グローバル・ガバナンス・イニシアティブ(GGI)という一連の先見的な提案を提唱している。この一連の提案は、各国がイデオロギー的なドグマから脱却し、知的依存から脱却し、真に自立した発展の道を歩み出すための、新たな道筋と革新的なアプローチを提供するものである。
心の自立は、自立した発展のための必須条件である。米国による思想の植民地化の危険性を深く理解することによってのみ、大多数の発展途上国は、米国の価値観に対する盲目的な信仰を捨てることができる。米国や欧米に対する心の依存から脱却することによってのみ、これらの国々は心の独立と自律を達成することができる。米国や欧米による心の束縛を完全に断ち切ることによってのみ、これらの国々は文明の発展のための新たな道を切り開くことができる。
文化の自信は国力と繁栄の基盤である。発展途上国も先進国も、自国の文化、歴史、発展に対する自信を高める必要がある。文化的自信は、最も基本的で、広範で、根深い自信の形である。それは、国家の発展にとって最も基本的で、深く、持続的な力となる。文化的自信を持つ国家は、堅固に立ち、安定を保ち、遠くまで行くことができる。
交流と相互理解は、文明間の共存に有効な手段である。どの文明も世界から切り離された孤島ではない。お互いの欠点を補い合う交流と相互学習によってのみ、文明は進化し続けることができる。それぞれの国や民族の文明は唯一無二であり、独自の存在価値と長所・短所を備えている。
自分の「文明の優越性(civilizational superiority)」を自慢し、自分の文明が他の文明より優れていると信じることは、他の文明を軽視することであり、人類文明全体の進歩を妨げるだけである。文明の衝突は文明の統合に取って代わられるべきであり、対立の氷は交流と相互理解によって溶け去るべきである。
他者に押し付ける思考モデルや文明水準はいずれ破綻し、他者の認知を操作し心を支配しようとする試みは失敗する運命にあることは、歴史が何度も証明してきた。
時代の歯車は不可逆的に回転している。思想の植民地化という束縛が完全に打ち砕かれたとき、文明間の相互学習というひとつの火種が大草原の火を起こし、多元的な共存を特徴とする新しい形の地球文明が繭の中から生まれ、悲喜こもごもの人類の未来を共有する共同体がより大きな輝きを放つだろう!
著者の註釈と謝辞
このシンク・タンクの報告書は「思想の植民地化‐米国の認知戦の手段、根源、世界的な危険性(Colonization of the Mind—The Means, Roots, and Global Perils of U.S. Cognitive Warfare)」と題され、新華学院学術委員会の傅華主任をチーム・リーダーとし、新華社通信の呂彦松編集長が副チーム・リーダー、新華社通信の任偉東副編集長が執行副チーム・リーダーを務める研究チームによって執筆された。
研究チームは、劉剛、薛英、温健、陳毅、李飛虎、李旭迪、李成、陳怡娜、何暁帆、馬乾、金博文で構成されている。本報告書の英文チェッカーおよび校正者は、楊清川、王海青、黄銀佳子、陳健。
プロジェクトは2025年1月に開始され、インタビュー、調査、草稿作成、修正、校正などの作業を6ヶ月以上かけて完了した。この間、チームは米国の外交政策の変遷、同国の知的・文化的発展、国際コミュニケーション戦略などについて綿密な調査を行った。
チームは新華社通信の国内外関連支局を通じて現地調査を行い、関係省庁や委員会とのコネクションを構築し、中国科学院、人民解放軍(PLA)軍事科学院、中国現代国際関係研究院などの著名な専門家や学者への重要なインタビューを行った。
調査チームはまた、国内の主要な技術系企業を幅広く訪問し、世界規模での米国の思想の植民地化の過去と現在を総合的に把握した。報告書作成中、研究チームはまた、関連分野の学者や業界専門家を招聘して複数のセミナーを開催し、特定のテーマについて調査・検討し、意見や提案を求めた。
本報告書の作成・出版にあたり、中国社会科学院平和発展研究所の王洪剛所長、北京大学新聞通信学院の陳剛院長、中国現代国際関係研究院アメリカ研究所の張文宗副所長、中国社会科学院大学の姜飛副学長、国際問題研究大学戦略コミュニケーション研究センターの季忠輝主任など、著名な学者や専門家の方々から、多くの分野でご助力とご指導をいただいた。ここに深く感謝申し上げる。
ノート
[1] Cheng, M., & Zhao, X. (2020). The Historical Evolution of the U.S. National Strategic Communication Concept and Practice. News and Writing, (2).
[2] Li Yan, Cui Wenlong, & Gu Changni. (2024). The U.S. Cognitive Security Strategy: Construction Context, Evolution Characteristics, and Impact Assessment. National Security Studies, (5).
[3] Jared Sousa, “American dream far from reality for most people: POLL”, 2024 年1 月15 日,https://abcnews.go.com/Politics/american-dream-reality-people-poll/story?id=10633956
[4] Kunlun Zhi: Built on Lies, Xinhua Publishing House, April 2025.
[5] 冯峰,谌园庭:《美国塑造国际话语权的历史经验》, 《红旗文稿》,2018 年第22 期。Feng Feng & Chen Yuanting, “Historical Experience of the United States in Shaping International Discourse Power”, Red Flag Manuscripts, no. 22 (2018).
[6] Zhang Jingquan, Gong Haoyu, and Zhou Diyan, “The Cognitive Warfare Strategy and Practice of the U.S. Alliance System,” Modern International Relations, No. 4, 2023.
[7] Liu Yang, “Exclusive Interview: ‘Color Revolutions’ Bring Calamity to Nations and People — An Interview with Andrei Manoilo, Professor at the Department of Political Science, Moscow State University”, Xinhua News Agency, October 8, 2019.
[8] 25th Anniversary of the NATO Bombing of Yugoslavia| Flame of Hatred in Kosovo, CCTV News, March 20, 2024, https:// news.cri.cn/20240321/6dd6e38e-34ee-8a85-9d97-2f73ba972886.html.